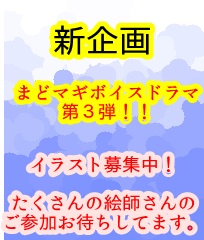ほむらの家族10話 『怨嗟』
「気がついた!ほむらちゃん?」
目の前にはパジャマ姿になったまどかがいた。
「びっくりしたなぁ。湯あたりしちゃうんだから!」
……湯あたり?
そうか、わたしはお風呂場で……。
記憶が曖昧で、何があったか今ひとつ思い出せないけれど。
「あなたが運んでくれたの?」
「えっと……うん。」
てことはつまり……。
み、見られたっ!?
「身体が冷えるといけないから、台所からストーブを持ってきたんだけど……ってどうかしたの?」
「いいえ。お陰で助かったわ……えっと……ありがとう」
「うん、無事でなによりだよ」
まどかの方は何も気にしていないようだ。
それはそうか……わたしの裸よりも、体調を気遣ってくれたのだろうから。
「その……助けてもらっておいて悪いのだけど、後ろ向いててもらってもいい?」
「あっ、ごめん、つい忘れてたよ」
慌ててまどかは後ろを振り向いて、わたしは一息ついた。
籠からパジャマを取り出して、それを握りしめる。
湯あたり? これまでそんな経験はない。
しかし、何故か晴れやかな気分だった。
よく覚えていないけれど、背中の疲れがとれたような……。
何にせよ大事に至らなくてよかった。
寝巻に着替えると、体が冷えないうちに二階へ向かった。
部屋に戻る前に、お母さんに風呂からあがったことを伝えよう。
お母さんの部屋は、わたし部屋から階段を挟んで丁度反対側に位置している。
部屋の戸をノックし、返事を待ってからまどかと一緒に入った。
部屋の中には居間の卓袱台のような高さの机が置かれ、こちらに背を向けて正座していた。
整然とした部屋の中には、質素と言っていいほど無駄なものが置かれていない。
電灯の代わりに、オレンジ色のナトリウムランプが机の上にあるだけ。
それ以外何の飾り気もない部屋の端で、筆をとっているようだ。
「先にお風呂いただきました」
「あら、まどかちゃん」
まどかが頭を下げると、お母さんはこちらを振り向き……。
「髪降ろしたのっ!やだ可愛い。可愛い!」
やれやれと思いながらまどかの前に立ちふさがった。
「用件は伝えたわ。もういいわね」
「さぁ、まどかちゃんこっちにおいで。ハァ……ハァ……」
息を荒くしているお母さんを妨げようと両手を広げた。
怯えながら、私の後ろに隠れるまどかを一目見て、これ以上ここにいる意味はないと思った。
「もういくわよ」
「ほむらちゃんばっかりずるいわ」
「どうせお風呂でたっぷりまどかちゃんを堪能してきたんでしょう?」
「あなたと一緒にしないでちょうだいっ!!」
わたしが怒鳴り散らすと、お母さんは一瞬の隙をつき、私の横をすり抜けて……。
「まどかちゃんっ!」
「ひっ!?」
「させないわ」
着物の帯を掴まえて、そのままこちらに引き寄せる。
が、凄まじい脚力に徐々にまどかの方へと進んでいく。
!?
なんて力だろう?
だが、わたしだって負けるわけにはいけない。
というか力比べで負けるはずがない。
「まどか、あなたは先に部屋に戻ってなさいっ!!」
「で、でも……」
「いいから。ここは私に任せて」
必死にまどかの名を呼ぶお母さんに遠慮しつつも、まどかは会釈をして部屋を去っていった。
障子が閉まる音と共に、お母さんはまどかの名を連呼しながら倒れ込む。
「ひどい。こんなのあんまりよっ!」
本気で悔し涙を流していたので、ため息がでた。
「お母さんからささやかな楽しみを奪って、ほむらちゃん楽しい?」
まるで理不尽な扱いを受けていると言わんばかりに涙で訴えかける。
わたしが悪いのだろうかと思ってしまうぐらいだ。
頭が痛くなる。
当分の間、まどかから目を話すわけにはいくまい。
「それはそうと、ほむらちゃんには一つ聞きたいことがあるの」
明かり一つの暗がりに響く声。
何故かぞくりと背中に冷たい悪寒が走った。
何を今更改まってと、思う。
まどかのことでも聞きたいのだろうか?
お母さんは、こちらから離れると、こちらに背を向け……
また卓袱台の前で正座をした。
――動けない?
何? まるで魔法にかかったみたい。
睨まれているわけでもない。
それなのに、背中から溢れ出る威圧感に圧されてか、全く動けなくなってしまった。
眉も動かない。まばたきすることも許されない。
声も……呼吸さえ。
――あれ、この光景。どこかで。
そして、お母さんはいつの間にかこちらを振り向き……放った。

むむむのむさん作
「どうして帰ってきたの?」
底知れぬ黒い瞳がわたしを捉えていた。
そこから感じられるのは怒りなどとおいう生易しいものではなかった。
こんな冷たい目をする人間がいるのかというほど。
ましてそれが自分の母親で、自分へと向けられているのが信じられない。
絶句した。
呆然と母を見上げるしかない。。
「ねえ、ほむらちゃん? 私の言ったこと忘れちゃったの?」
「帰って来なくていいって言ったよね?」
「っ!?」
わたしの中で、蘇った。
忘れていた記憶。
なかったことに……消してしまいたかった記憶。
それが……重なる。
「この2年でいったい何があったのか。お母さんに聞かせてみなさい」
あらゆる呪いや怨嗟を見てきたというのに、母の抱える闇には耐え切れず戦慄した。
皮肉にもその恐怖が、忘れていた過去を呼び戻した。
千里の彼方にあったはずの母の顔が、目の前にある母の顔とぴったりと重なるのだ。
まだ小学生だった私に身も凍るような寒さを浴びせ、痛めつけたあの顔。
――もう二度と帰ってこなくていいから。
いてもたってもいられなくなりその場から立ち去った。
廊下の片隅で、木造の柱に体重を預けた。
「はぁ……はぁっ……」
発狂し叫びだしたいのを必死でこらえ、両腕を組んで恐怖を鎮める。
大丈夫だ。大丈夫。
あの人はここまで追ってこない。
――あれ……。わたし。
思い出してる。
お母さんのことを。いつの間にか思い出している。
思い出して……しまった。
――断片的で、未だ朧げではあるけど、あの人が私に何をしてきたか……思い出してしまった。
お母さんは……私のことが嫌いだったんだ。
昔から。
ギリリ、と歯を噛む音がした。
冷たい汗が背中を伝って気持ちわるい。
やり場のない悲しみと怒りが、そして心のない言葉がわたしの中で反芻する。
『二度と帰ってこなくていいから』
忘れるべきではなかった。
あんな強い嫌悪を、何故今まで忘れられたのか不思議でならない。
知っていたら、こんな場所に帰ってくることはなかったのに。
二度と会うつもりなんてなかったのに……。
まだあんな憎まれているとは思わなかった。
わたしはお母さんに家から追い出された。
だから正月にも帰らなかったし、二度と会おうなどとも思わなかった。
家を出てからというもの、入院しても見舞いにくることもなければ、便りを寄越すことさえなかった。
徹底して自分を突き放し、無視して……。
その理由も当時から予測はついていた。
仕事を。
あの人の生きがいを奪ったから。
あの人が何をしたかったのか、望んだのかは知らないが、
おそらくそこへ戻ることができないのだろう。
その原因はほかならぬわたしのせい。
病気がちだったわたしの面倒を見ざるをえないから、退職したのだ。
昼間、屋敷で床に手をついて一生懸命磨いていた姿を思い出す。
このだだっぴろい家を管理するだけの日々に虚しさを感じた。
あの人が望んであんなことをしているとはとても思えなかった。
それを忘れるために、家で働き、そして一日が終わる。
家政婦を雇わないのはそのためだ。
何も考えない――ただ一日何も考えず過ごすために。
ただこの家に、埋もれることになってしまったんだ。
――わたしのせいで。
そして終日まで家事に精を出すことで、気を紛らわしているに違いない。
身体の弱いわたしを引き取ったが最後、こうなることを運命づけられたのだ。
「そんなの私を生んだ貴女が悪いんじゃない!」
不当な呵責に対する怒りがわいてきた。
悪いのは全てを子供のせいにして、責任をなすりつけているのはあの人の方だ。
わたしが何をしたというの?
ただあの人たちの都合で生まれてきただけだというのに、責められる謂われはどこにもない。
――わたしを弱い身体に生んだ、あなたが悪いんじゃない。
おかげでどれだけ苦労したか。
友達も、勉強も、まともに学校に通うことさえままならない。
悔しくて涙が止まらない。
自分に理があることを知っている。
どう考えてもこちらが悪いはずがない。
「わたしは悪くないのに……」
それなのに母の生きがいを奪ってしまった。
――私のせいで……私のせいで。
あの人の心を壊してしまった。
自分さえいなければこんな古い屋敷に囚われることもなかった。
あの人は幸せでいられたのだろうか。
笑っていられたのだろうか?
――嫌。
わたしはあの人に迷惑かけるつもりも、恨まれるつもりもなかった。
どうしたらよかったの?
生まれてきたのがいけなかったの?
ねえ、まどか……。
膝を抱え、しばらく暗闇の廊下の中でうずくまった。
湯気を放っていたぽかぽかの身体はすっかり冷えきってしまった。
――まどか。
まどかが待っている。
早く部屋に戻ろう。
深呼吸をして、まどかが待つ障子戸を引いた。
「あ、ほむらちゃん。お帰り」
まどかの笑顔だけが自分の支えだった。
まどかのためならいくらでも辛いことだって乗り越えられる。
これまでそうしてきたように。
ボロボロになってしまった心を落ち着けて……微笑みかける。
「ただいま。もう布団に入ってしまったのね」
「えへへ、このお布団ふかふかで気持ちいいよ。ほら、ほむらちゃんも早く!」」
「待って。今片付けるから」
現実から目を逸らしているのではない。
あの理不尽を忘れることなどできないだろう。
この憤りを忘れることもできなければ、申し訳ない気持ちも消えることはない。
――それでも、わたしはまどかが大事だから。
ここで絶望するわけには行かない。
怨みや、絶望の感情はソウルジェムを摩耗させ、死へ近づく。
今までだって心を閉ざし、どんな理不尽なことも我慢してきた。
――大丈夫。私はあの頃のままじゃない。
それに、今はまどかがいてくれる。
大事なものを忘れてはいけない。
例え母が怨嗟の亡霊と化したとしても、それに引きづられてはダメだ。
わたしはこの世界と……まどかを守るために生きている。
まどかとともにいられることを糧に生きている。
そして、それはきっとまどかも同じで……。
――こんなところでつまずいてたまるか。
深呼吸。
そして部屋にあったハンガーに上着をかけて、窓際に吊るす。
窓に寄るだけで、外の冷気が伝わってくる。雪はまだ止んでいなかった。
「まだ降ってるわね。明日も外出できないかもしれないわ」
「それじゃあ、お掃除でも手伝おうか。明後日は大晦日だもんね」
そうね……と、わたしは平静を装いながら頷いた。
大掃除。全部あの人がやると言い出しそうだ。
……
「ほむらちゃん?」
「……え?」
「どうしたの、なんか今怖い顔してたけど……」
「気にしないで。 雪かきが億劫だって思っただけだから」
「そっか……それならいいんだけど」
あの人は家事以外にやることがないのだろうか。
飾りげのない母の部屋。
棚には、数冊の本が置かれているだけで……。
卓袱台とベッドの他には、気持ち悪いぐらいに何もない。
体が冷える前に、布団に入った。
まどかの言うとおり、今のわたしの家で使っているものよりも高級感があり、柔らかくて厚みがある。
お客様用の布団にしておくのは少し惜しい気がした。
見滝原の家に持って帰ったら、まどかが喜んで一日中篭っていそうだ。
「うぇひひ、あったかいね~」
まどかはにこやかに笑うと、布団の中に顔を埋めた。
それを見ているだけで心が和んでいくのがわかった。
やはりまどかを連れてきてよかった。
ほっと一息つくと、腹のあたりに冷たい何かが触れてきた。
「きゃっ!?」
思わず悲鳴を上げると、布団の境界からまどかが顔をだした。
「えへへ、冷たかった?」
まどかは布団を伝って潜伏しながら移動してきたのだ。
冷たかったというより、何が起きたのかわからずびっくりしたというのが正直なところ。
まさかまどかがそんな子供っぽい遊びをしてくるなどとは思わなかった。
不敵な笑みを浮かべ、まどかに近寄った。
「わわ。ほむらちゃん、もしかして怒ってる?」
「いいえ、全然そんなことないわ」
ニヤリと笑ってまどかに向かって手を伸ばすと、焦りながら布団の中に隠れるまどか。
すぐに布団を引きはがし、まどかの脇腹を掴んで拘束する。
するとまどかは逃れようと暴れるが、本気ではないようだ。
とりあえず背中に手を突っ込んでみた。
「ひゃあ、冷たい。冷たいよほむらちゃん」
どこか余裕のあるところが気に入らなくて、さらにその手を脇腹に伸ばす。
「ちょっ、ほむらちゃん。そ、それだけはやめてっ!」
「ふふ。だってまどかったらまだ苛めて欲しそうな顔をしているんだもの」
まどかは涙を浮かべながら抵抗した。
「きゃはは、や、やめて。脇は反則だよっ!」
なんだか嬉しくなって、構わずくすぐり続けた。
まどかが根をあげるまでやってやろうと思ったが、家族に聞かれるのも嫌だったので、頃合いをみてまどかを解放する。
「あ~あ、布団がぐちゃぐちゃになっちゃったよ」
「敷き直すわよ」
わたしの中にあったもやもやはいつの間にか片隅に追いやられていた。
消えたわけではないが、笑うまどかを見ていたら不安や苛立ちもなんて吹き飛ばせそうな気さえした。
いや……
そんな単純なものではないか。
あの人はきっと、どこまでもわたしのことを蝕んでくる。
それを甘んじて受け止めるくらいしかできないのだろうか?
二人で布団を敷き直して、もう一度床に就いた。
「ほむらちゃん、そっち行っていいかな?」
うん……。
「断っても、朝になったらこっちに来てるんでしょ? 」
寂しい……つらい……。
でも。
まどかにそんな情けないことを言えない。
「じゃあ、そっちいくね」
まどか両手にまくらを抱えてこちらの布団へと来る。
「……」
ああ……
何故だろう?
胸の奥が詰まるような気持ちがして……。
まどかに背を向けた。
「お邪魔します」と、声をかけて、まどかの手足が布団の中に潜りこむのがわかると、胸のあたりが痞えて……。
落ち着かないのはどうして?
怖い……。
まどかといると、胸が苦しい。
それなのに、今日はいつも以上に触れていたい。
それはきっと、あの人の毒気に当てられたせいだ。
3年前……いやそれ以上前から、私を苦しめ続けたあの目。
今の母が怖いかと言われればそうでもないが、あの目と敵意はしばらく忘れられそうにない。
「まどか……」
「どうしたの?」
「……」
くりくりとした瞳がわたしを捉えている。
刹那、腕を伸ばそうとするも、わたしの自尊心がそれを押しとどめた。
……自分がおかしいという実感があった。
まどかのことを窘(たしな)める位置にいたはずのわたし。
それが……どうしてこんな……。
あの人のせいだ!
全部……ぜんぶあのひとのせいで、こんな情けない……。
つん。
まどかの鼻先が鎖骨のあたりに押し付けられた。
次いで顎が胸に収まる。
じれったくて焦りを感じた。
同時に、そのことをまどかに悟られてはいけないという
早く……その両腕で強く抱きしめて欲しい。
わたしが逃げられないぐらい強く、強く。
どうしたらまどかが抱きしめてくれるだろうかと思案した。
まさか抱きしめてなんて、恥ずかしくて言えない。
とりあえず、右手で彼女の頭を撫でおろす。
長く柔らかい髪が手によく馴染んでいる。
嬉しそうに鼻先を腹に擦りつけてくる。
くすぐったい。
でも、それだけじゃ足りない……。
そんなわたしの念がとどいたのか、まどかはわたしの身体を掴んだ。
しかしそこは、腰の上のあたりだった。
不満に思ったわたしは、まどかに気づかれないようちょっとずつ身体をずらして、その腕がもっと体の上の辺りに来るように移動した。
布団の暗闇の中で、まどかのおでこが近くにある。
髪からは新しいシャンプーの香りがして、鼻腔を擽った。
しかし、もっと強い力で抱きしめられるほうがいい。
ただ背中に手が触れるだけでは足りない。
しばらくまどかの髪をなで続けていると背中にかかるが緩み、寝息が聞こえてきた。
まどかの背中に両手を伸ばし、起きださない程度の力でぎゅっと抱きしめた。
結局わたしの中に一抹の切なさが留まり続けた。
朝になったらもっと強くまどかが抱きしめてくれていることを祈り……眠りについた。