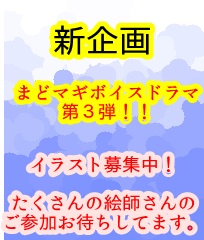ほむらの家族6話 『愛憎』
魔法少女まどか☆マギカ ~ほむらの家族~
【第五話 愛憎】
障子戸を閉めると、わたしは胸に痛みを感じて両手で押さえた。
――な、なんでいきなり手を握ってくるのよ。
ていうか、そんなことぐらいでどうしてこんな……。
心臓がバクバクいって収まらない。
まどかに手を握られた瞬間、顔が熱くなって…恥ずかしくて。
顔がまともに見れない。
――どうして?
なぜかまどかに触れられると思った瞬間、思わず逃げ出してしまった。
今までこんなことなかったのに。
とにかくこのままでは二人の間に隔壁ができてしまう。
ヘタをすればまどかに嫌われてしまうかも。
原因を突き止めないと。
「珍しく慌てているようだね、暁美ほむら」
「なに? よんだ覚えはないわよ」
「君にしては、魔力と感情の波長に乱れを感じたからね。人の感情は僕たちの研究課題でもあるんだ」
「もし僕で良ければ、力になるよ」
「ならもう少し、人の気持ちを推し量ることができるようになるべきね」
「モルモットにされると分かって、協力する人間はいないわよ」
「きみは目的をきちんと話さなければ、動こうとしないじゃないか」
それだけあなたのことを信用してないということよ。
「別にあなたに話すつもりはない。協力も必要ない」
感情のないものに、人の気持ちがわかるはずがない。
しかし、キュウべぇは構わず話しを続けた。
「君はこの家に来るまで、ずっと負の感情を抱えていた」
「あなたたちには、感情なんて理解できないでしょう? どうしてそんなことがわかるの?」
「無論、僕たち自身が人間の感情を実感することは不可能だ」
「けど、君は知っているだろう? 人間の感情はエネルギーに変換することが出来る」
「感情にはそれぞれ、おおまかに正か負のポテンシャルを持っていて、その絶対値こそがエネルギーになるんだ」
「だから君たちのことを研究すれば、さらに明るい宇宙の未来の姿を模索できるというわけさ」
「要するに人の気持ちを、石油や水なんかの資源程度にしか考えていないということね」
インキュベーターの考え方そのものを嫌っているわけではないけど、煮え湯を飲まされ続けたからせいで、刺のある言い方しかできなかった。
「話しを戻すとしようか」
「君の負の感情はおそらく両親に会う不安によるものだと思うけど、それが一瞬で開放された場面がある」
「暁美ユキが鹿目まどかに抱きついた時だ」
「あの時、マイナスに傾いていたパラメーター指数が瞬間的にニュートラルに回復した」
「これがこの家に来てから最も、エネルギー変化が大きかった地点だよ」
わたしは家族に会うということで、極度に緊張していた。
マイナスに傾いていたというのは、期待よりも不安の方が大きかったということか?
それがゼロになったというのは、緊張の糸が切れた時。
「そしてゼロになったポテンシャルは数秒後にわずかだけどそれまでを超える数値でマイナスを示した」
「どうだい、少しは参考になったかい?」
「え、ええ……」
キュウべぇにしては意外なほどまともに情報提供してくれた。
「ちなみに、その時に生じたエネルギーギャップは、やかんの水を沸騰させるほどの熱量に変換することができる」
「そんなことどうでもいいわよ」
「で、情報提供はありがたいけど、あなたは何が知りたいの?」
「さっきも言った通り、人類の行動科学には今後の宇宙の未来がかかっていると言っても過言じゃない」
「僕が興味があるのは、どうして君が鹿目まどかを避けているのか、その理由についてだよ」
「あれほどまどかを慕っていた君が、彼女遠ざけているか興味深い」
なるほど。ようやくつかめてきた。
情報がもらえるなら協力するのはやぶさかではない。
しかしキュウべぇの話からすると、わたしのことを常に観測していてもおかしくない。
24時間体制で監視されていると考えただけでぞっとする。
「消えなさい。 あなたの質問には答える意志も義理もないから」
「十分真摯に話しをしたつもりだったんだけどなぁ。 やっぱり人のことはよくわからないね」
そして、白い獣は姿を闇の中に消した。
あんな連中に四六時中ストーキングされていると思うと鳥肌が立つ。
素直に諦めてくれればいいのだけど。
だけど、ヒントを手にいれることはできた。
あの時――まどかがお母さんに抱きしめられた時、わたしは何を思った?
ああ。そうだ。
あまり思い出したくないけど……
正直に答えるなら『どうしてまどかを?』と思っていた。
少なからずわたしは、母に優しい言葉を期待していた。
家族に会いに来た。私を歓迎してくれる家族に。
こんなこと、記憶を忘れてしまった私が期待するのはおこがましいのだけど……。
わたしはただ……温もりが欲しかったんだ。
それなのに、あの子が……。
まどかが……。
「!?」
まどかは悪くないじゃない!?
何を考えているのわたし……。
だって、あの子はただの被害者じゃない。
わたしの用事に付き合って、それで……。
『そしてゼロになったポテンシャルは数秒後にわずかだけどそれまでを超える数値でマイナスを示した』
まさか……わたしはまどかのことを……。
まどかと同じぐらいとは言わずとも、母から愛される自分でありたいとどこかで願っていた。
顔も思い出せないあの人たちの温もりが欲しかった。
お父さんは「お帰り」と、わたしのことを撫でてくれた。
愛情を向けてくれた。
それがどれだけ嬉しかったか。
だけどお母さんは?
なぜお母さんはわたしを抱きしめてくれなかったの?
どうして隣にいたまどかを抱きしめたの?

むむむのムさん作
あの子は、未だに両親に愛されている。
形は消えてしまっても、絆は消えていなかった。

ゆきもちさん作
――それなのに……。
それなのに、あなたは私のお母さんまで?
だから……。
だから? 憎いの?
まどかのことが?
そんなことあるわけない。あってはいけない。
これまでわたしは何のために戦ってきたの。
時間を超え、何度も何度も結末を変えようとしてきたのは何のため?
まどかを守るためではなかったの?
そのわたしが、どうしてまどかを避けなければいけないの?
あの子は今、この世界でわたしを必要としてくれている。
そのわたしが、遠ざけたら、まどかはいなくなってしまう。
そんな気がする……。
「いやっ!」
まどかを嫌いになりたくない。
あの子を手放したくない!
『そしてゼロになったポテンシャルは数秒後にわずかだけどそれまでを超える数値でマイナスを示した』
――認めない。私は認めない。
まどかを羨ましいなどと思わない。
まどかを嫌いな自分などいるはずがない。
部屋の外から足音が聞こえたと思うと、そっと明かりが灯った。
「久しぶりだから、電気の場所忘れたか?」
お父さんだった。
わたしはいつの間にか台所の机の傍でうなだれていることに気が付いた。
そういえば、お茶を沸かしにここまで来たことを今になって思い出した。
「電気をつけなくてもお湯ぐらい沸かせるもの」
やかんを見て、なるほどとお父さんは頷いた。
「どうしたの?」
わたしは努めて淡々と話しかけた。
これでいいのだろう。
昔の自分を演じる必要もないのだから。
「いや、夕食を食べてなかったから少し心配になっただけだよ。元気ならそれでいいんだ」
こんな冷淡な返事、悪態とも思えるような行動は、昔のわたしなら絶対にしなかった。
それなのに、お父さんは何も不審に思っていないようだ。
わたしの仮説は正しかったんだ……。
せっかくお父さんのことだけは思い出せたのに、悔しくてたまらなかった。
これは家族のことを忘れていた報いなのか……。
お父さんは机の反対側の椅子に腰をかけた。
話しがしたいようだ。
お父さんから聞きたいことはあるけど、今はとてもそんな気分にはなれなかった。
「部屋でまどかが待っているからもう行くわ」
「ふふ、まどかちゃんに娘をとられちゃったか……残念だな」
「!?」
それはまるであてつけのような発言だった。
まどかを追いかけ、家族を棄てた自分への。
もちろんお父さんにそんな意図がないことぐらいわかっていた。
しかし、その一言はわたしを震わせた。
「お母さんと一緒にしないでっ! わたしはあの人とは違うんだからっ!!」
病気の母を本気で毛嫌いしていたわけじゃない。
ただ、申し訳なくて……やり場のない想いをぶつけてしまった。
わたしは後ろを振り向けずにいた。
きっとお父さんは寂しそうな顔をしているんだと思う。
久しぶりに会ったのに、思いもよらない言葉を浴びせられて。
「少し言い過ぎたわ。ただ、私はまどかとのことを勘違いして欲しくないの。まどかは大切な友達よ」
別にお父さんに誤解されようが、さして気にもとめない。
大事なのはそんなことじゃない。
わたしは、この人との距離の取り方がわからなくなってしまったのだ。
「……ユキのことは、嫌いか?」
「お母さん?」
そんなの決まっている。
好きでも嫌いでもない。
思い出がないのだから。
もし嫌いだと言い切れればどれだけ幸せだろう。
そして、お父さんのように少し記憶を取り戻したところで、それは大した意味を持たない。
その思い出は、わたしとお母さんを結ぶものじゃない。
「ねえ。こんなことを聞くのもなんだけど、あの人は本当に私のお母さんなのかしら」
まどかに尋ねたことを父にも質問した。
会話に困ったから自然と出てきた言葉がそれだったのだ。
こんなことを聞いたのは、もちろん理由がある。
お父さんのことは思い出せたのに、お母さんのことは全く思い出せないからだ。
実はわたしにはお母さんなんていなかったんじゃないか?
その方が救われるような気さえした。
「ほむらが認めたくないのもわかる。でもあれがお前の母親だよ。残念だったな」
お父さんは笑った。
それが意外だった。
怒られると思ったのに。
お母さんの変態ぶりにはお父さんも困り果てているのかもしれない。
わたしも笑った。八つ当たり混じりの冗談をいった。
「嫌いな相手を好きになるにはどうしたらいい?」
「なかなか辛辣だな……」
お父さんはお母さんのことを言っていると思っているようだった。
別にわたしはあの人が嫌いなわけじゃない。
ただちょっと残念なだけだった。
それよりも、わたしにとって大事なのは、まどかのことだ。
「そうだな……自分を騙すこと……かな」
「自分を騙す?」
「そう。好きだと思い込めば、そのうち自然と仲良くなるもんだ。たとえどんなに相手のことを憎んでいてもな」
大人の世界は、複雑なのだんう。
年をとるだけ嫌いな人との付き合いも増えるのかもしれない。
「ユキは昔からあんなだもんな。ほむらはよくまっすぐ育ったって思うよ」
「まっすぐだなんてとても思えないけど……」
「でもな、あいつもお前の看病が出来るように、仕事を辞めたんだよ」
「そうなの?」
「ああ。それなりに仕事に情熱もあったみたいだし」
お母さんが、わたしのために?
「私って、昔っから身体弱かったものね?」
「そうだな。何かあるとすぐに保健室に運ばれて、学校から電話がかかってきたな」
虚弱な体質に関しては、改変の影響をうけていないようだった。
身体が丈夫になったのは魔法少女の影響だから。
「じゃあ、そろそろいくから」
わたしはは湯呑みをお盆にのせ、二階へと上がった。
あの口調で喋っていてもお父さんは驚かなかった。
私はいったいどんな娘だったんだろう。
幼いながらに、随分と生意気な女の子だったのかもしれない。
今のところわかっているのは、病気がちでお母さんには手をわずらわせていたということぐらいか。
それよりも今はまどかとどう向き合うか。
それだけを考えよう。
今更わたしがここに戻る資格はない。