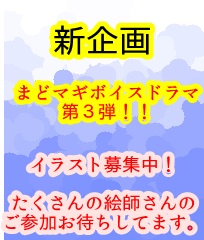ほむらの家族1話 『再会』

ラテ・ラピクさん作
そろそろ夜明けか。
携帯電話の右上にある時間表示を確認しながら気が重くなった。
夜行バスの窓は雪のせいか曇っていて外の景色はほとんど見えず、凝結した水泡を眺める。
日付にすると何日、いえ……何年ぶりなのかしら。
時の流れだけみればほんの一年半に過ぎないけれど、折り重なる時間移動のせいでもはや永遠とも感じられるような時間を見滝原で過ごしてきた。
携帯の連絡先一欄を開くと真っ先に目に入る二つのデータ。
暁美敏和、暁美ユキ。
名前を見ながら、二人の顔をイメージする。
しかし、全く思い出せない。
もしうっかり彼らに道端で出会ったと思うと、うすら寒くなるのを感じた。
携帯で実家に帰省の連絡をした時のこと。
「あら、ほむらちゃん。どうしたのかしら?」
声を聞いても、その相手が女性であるということ以外わからない。
名乗る前に、自分の名前を呼んでくれたお陰で助かった。
電話先の相手が母親とは何の関係もない相手とも限らないから。
「……明後日そっちに帰るから。それと……」
用件を手短に伝えると、『わかった、じゃあ待ってるね』とだけの一言。
電話を終え嫌な汗をかいて、手が湿っていた。
罪悪感と、憤りが胸にのしかかる。
いつも通りの自分を装うことでいっぱいだった。
約束なんてしなければよかったのに。
約束。
それはわたしが心の支えとしている親友と交わしたものだ。
家族に会いに行く。
まどかに勇気づけられ、誓いをたてた。
そのせいで家族に逢いに行くはめになってしまった。
繰り返し、繰り返し時を巻き戻してきた。
わたしはその無限とも思えるような環の中で、失ったものがいくつかある。
そのひとつが『家族の記憶』
運命を変えるということはとても過酷なこと。
身を持ってわたしはそのことを知った。
どんな犠牲を払ってでも、まどかを救い出してみせるという望みを叶えるため……。
気がついたら、わたしには何もなくなっていた。
何度まどかが死ぬところを見たのかわからなくなった頃には、母や父の像はもう……。
東の空が少し明るくなる頃だが、吹雪のせいでバスの中に光は届かない。
再会の時が刻々と近づいていると思うと深い溜息が出た。
「大丈夫、きっと思い出せる」
独り言のような声。
そうだといいのだけれど…
わたしには気がかりなことがいくつかある。
そのうちの一つは、本当に家族から心配されているかということ。
どのような理由で家を出たのかは既に記憶にないが、中学にあがるばかりの一人娘を持つ親としては、考えにくいことだった。
よほどしっかりした精神と正常な健康状態であれば有り得る話なのかもしれないが、わたしはそのどちらも持ちあわせていなかったはずだ。
それだけではない。
何度も何度も同じ繰り返してきたが、家族からただの一度も連絡がなかったことも気がかりだった。
どの時間軸、どの世界でも、それは変わらなかった。
何があろうと、携帯電話に着信はない。
ここまでくるといよいよ嫌な予感を禁じ得ない。
家族の記憶を失ってしまったわけだが、両親からの音沙汰が皆無であったことが要因の一つといえる。
「もし、受け入れられなかったら……そのときはどんな顔をすればいいと思う?
ねえ、まどか」
六時二十三分青森駅到着。
見滝原では見ることの出来なかった深雪と凍えるような冷風が出迎えてくれた。
おかげで眠気が一気に吹き飛んだ。
後ろから『こんな雪見たことないよ』という感嘆の声が上がるが、鬱蒼とする以外ありえなかった。
北の国の生まれといえ、親しみもない。
雪に馳せる想いが何もない。
白くて冷たいものが、ただ目の前を遮って視界を奪うだけで益体もないもの。
それがひどく寂しく感じた。
交通状態がこの大雪で麻痺しないところを見るに流石雪国といったところだろうか。
見滝原(あちら)に長くいたおかげで気づいたが、身長をゆうに超えるほどそびえ立つ白い塊をかき分け、車を動すのは至難の業だろう。
実家はもっと豪雪に見舞われているのだろうか。
颯爽とJRの構内まで走りぬけ、防寒着の雪を払いながら、財布と乗車用の電子カードを取り出した。
関東で使われているものと型が違うが、代用できるのか?
駅員に改札で尋ねると、ここでも相互利用が可能らしい。
電子カードのポイントを券売機でチャージし、駅のコンビニでお茶と握飯を二個ずつ購入した。
食欲はなかったが、何も食べないと長旅で身体が持たない。
函館行き白鳥号が停車していたので、身体が冷えないうちに早々と乗り込んだ。
空席を見つけるとほむらは荷を上棚に起き、放心したように座席に凭れかかった。
バスの窓とは違い、くっきりと外の様子が見える。
窓際の乗客が朝食をとっていたので、ほむらもレジ袋から梅にぎりを取り出した。
まもなく白鳥二十号が発車する。
数時間後には本州を離れるだろう。
『今なら、まだ帰れる』
開けなくていい蓋を、開けようとしているんじゃ……。
しかしその選択はできない。
既に退路は断たれている。
まどかと交わした約束。
この重みから、逃げることはかなわなかった。
窓際の乗客が、窓の雪景色を物珍しそうに眺めていた。
ほむらも、その視線の先を追ってみると、果汁園が一面にある。
と思えば、白い山が連なっていて、景色は次々と変化していった……。
電車に揺られ旅をするのが嫌いじゃない。
幼少のことはほとんど覚えてないが、流れる景色を見るのが好きだったんだと思う。
病気がちだったこともあって、病院にいることが日々の大半を占めていたから。
その時は祖父の家に預けられていたことは記憶にある。
憶えてるのは家の中、学校、病院の3つだけ。
毎日似たようなものを見て、似たような日々を過ごしていた。
だから日常とかけ離れた遠出に憧れたんだろう。
電車でどこかに連れていってもらうだけで、その日は何より素敵な体験をしたと、胸を踊らせ。
そう――窓際だけは譲らない子供だった気がする。
何の因果か……
同じ景色ばかりを繰り返し、繰り返しみてきたのだ。
目に焼き付いて、離れないほどに。
同じ景色を──いつもいつも。
青函トンネルを超えると、吹雪が出迎えてくれた。
故郷に近づけば何か母たちのことを思い出すかと思ったけど、そんなことはない。
本州を抜けても代わり映えのしない雪景色が広がっているだけだ。
別段懐かしいとも思わない。
億劫な瞬間が近づいて憂欝になっただけ。
このままどこか別の所へ旅行に行ってしまいたかった。
隣にはまどかを連れて……
できるなら暖かいところがいい。
しかし函館に到着すると、呪われたように札幌行き列車へと歩ませるのだった。
仮に父と母に会ったとしよう。
昔のような気弱な姿を演じるをべきなんだろうか?
染み付いてしまった行動や習慣は直すのが難しいように、言葉遣いや雰囲気は急に直せるものではない。
必ずぼろがでるだろう。
長年培った思考はもはやあの頃の自分とは程遠い。
知ったことか。あの人たちはどうせわたしのことなんて心配してない。
どこか諦めに似た気持ち。
ごめんなさい。忘れてしまって、ごめんなさい。
胸が潰れてしまうような罪悪感。
まるで反対の二つの気持ちが入り交じって、どうしていいかわからなかった。
この三つ編みとメガネはそんなの迷いの現れだ。
鏡の前でまどかを守ることもできずに、ただ甘えることしかできなかった頃の自分の思い出。
強さへの憧れを抱いたのも、彼女を守る自分になりたいと願ったのも同じ時。
その頃の生き姿を鏡で見て、苦笑いするしかなかった。
よくぞここまできたものだと自分を褒め称えたい気もするし、あの頃の自分はもういないのだと切なくもなった。
札幌に着いたのは昼過ぎ。
見え覚えのある構内につくと、更に憂欝になった。
駅の食堂で暖をとっていると、観光に来ている大学生らしき団体が目についた。
連中のように暢気にふかし芋でも食べて行ければよいのだが、そんな気分ではない。
ぞろぞろと人が集まってきた。
万一声をかけられてはたまらないので仕方なく立ち去った。
;黒背景
駅のロータリーでタクシーを捕まえると、トランクを荷台に積み込んで雪を払い、行き先を告げた。
雪がなければ十分歩いていける距離だったが、長旅で疲れているであろう身を案じたのだ。
それにうっかり道端で顔のわからない親に出会ってしまったら最悪だ。
自分を知っている人物に出会ってもわからないのだから。
タクシーに乗り込むと「高校生かい」と運転手に尋ねられる。
バックミラーには、しわの寄った六十近くの年長者の顔が映っていた。
自分は中学生だと答えて、それっきり押し黙る。
話したくないオーラを十分出していたはずなのに鈍感な運転手は観光に来ていると思っているせいか、聞いてもいない札幌周囲のことを楽しそうに話すのだった。
この手のサービス業者はどうして、話し好きが多いのだろうとうんざりした。
いっそここは地元なのだから、そんな案内話いらないと言ってやろうか。
事実男は見憶え聞き覚えのあるものの話しかしなかった。
家族のことは思い出せないくせに、どうでもいいことだけはしっかり覚えている自分がまた嫌になった。
運転手の退屈な話を聞き流し、流れる景色を見ていると胸の奥がじりじりと締め付けられる感覚が増していった。
動く風景を見るのは好きなはずなのに、今は何をしていても胸が詰まるだけだ。
最後に一度携帯で父と母の名前を確認した。
――暁美敏和、暁美ユキ。
これがの両親の名前らしい。
;暁美家前
実家は古い住宅街の区画に位置していた。
中でもわたしの家は古い部類に入ると思う。
外から見てもわかるくらい結構な広さの庭をもつ家。
堂々とした青塗りの塀が目の前にそびえ立っていた。
二人で暮らすにはもったいないほど広壮な土地。
家はもともと父の実家だったと聞かされている。
よほどの名家だったのだろうが、記憶では父の両親には会ったことがない。
祖父たちは同居していなかったはずだが、もしかしたら既に亡くなっているのかもしれない。
門をくぐり、玄関の前まで新しい足跡をつけていく。
ある程度雪かきをした跡が見られるものの、既に石畳の上に新雪が降り積もっていた。
足音が重なってズブズブと音をたてながら進む。
結局逃げられなかった。
もはやそういう運命だったと思い諦め、
ゆっくりと玄関の戸を叩いた。
頻りに胸の鼓動が響く。
誰も出てこないことを祈り……
そして吹雪の音だけが虚しくその場に鳴っていた。
家の中から物音ひとつしない。
願いは届いたかのように思えた。
このまま駅まで戻り、どこか旅行にでも……。
「どうしたんだろう……」
――いいじゃない。
いないならいないで、帰ればいいのだ。
まだ冬休みは始まったばかり。
二人で家でだらだら過ごすのもよし。
旅に出かけるのもよし。
『早く……』
その言葉を口にしようと、門の方に踵を返した瞬間。
扉は開かれ……
その人は現れた。

むむむのむさん作
背丈は美樹さやかぐらい……いやそれ以上あるだろうか。
透けるように白い肌が印象的だった。
顔立ちは凛として、底知れぬ深い黒い瞳をしている。
詢子さんのような覇気はないが、聡明そうな落ち着きと奥ゆかしさを感じた。
紫の着物に身を包み、それが古い屋敷によく似合っていた。
出で立ちのせいか、日本の女性らしい。
自分の母親かもしれない相手なので憚られるが、一言でいうなら美人だった。
目が合った。
驚いたとも、笑っているとも思えない目。
視線に温度を感じない。
まさかこの状況で現れた相手は、母親ではないというのだろうか?
いや、そんなはずはない。
そんなはずはないのだが……。
何を言えばいいのか。
『ただいま』
『なぜ、わたしを家から追い出したの?』
『どうして、連絡をくれなかったの?』
『ごめんなさい……』
どの言葉も想いを伝えるには足らない。
この気持を伝えるには、今までの時が重すぎて、崩れてしまう。
目頭が熱くなった。
――ああ、わたしは本当に馬鹿だ。
涙が出そうになったのは『その人』に焦がれるような懐かしさを感じたからではない。
こうして体面しているというのに、本当に彼女のことが思い出せないのだ。
この人とのつながりの一粒を記憶の中から手探りで探し当てようとしても、そんなものありはしない。
――この人に間違いないのに、わたしは……わたしは……
カタカタと下駄の音を鳴らし、勢いよく足元の雪を蹴散らしながら向かってきた。
「なっ……」
こちらに向かってくる。
嬉々とした表情で……。
ものすごい速さで……。
そんなに、再会を待ち焦がれていたというのだろうか。
だとしたら、自分はとんでもない疑いを向けていたことになる。
家族が自分のことを放りだしたのは、何か事情があって、決して自分のことがどうでもよかったわけではない。
一方的に忘れて、一方的に……。
――ごめんなさい。
その言葉を口にしようとした時だった。
自分に向かってくるはずの女性は、予想外方向へその手を伸ばした。
「わっ……」

ぷにゃーさん作
隣で悲鳴にも似た狼狽の声が上がった。
女性は嬉しくてたまらないといった様子で、隣にいる少女をぐいぐいっと抱きしめる。
見滝原からずっとずっとつないでくれていた手が、母親らしき人によって断ち切られた。
「ほむらちゃん、この子があなたの言ってたお友達ね! ねぇ、お名前はなんて言うの?」
思考が停止する。
目の前には、まるで子供が子犬とじゃれる楽しそうな光景が繰り広げられていた。
ただし片方は母親で、もう片方は親友。
まどかが「助けて」と言わんばかりにこちらを見ているが、あまりにも予想外の出来事にただ呆然とするしかなかった。
この時から既に嫌な予感はしていた。
一度迷いこんだが最後。
抜けること適わない蜘蛛の糸に絡め取られるようにズルズルと引き寄せられていたのである。
糸を引く主は、この目の前でまどかと戯れている女性。
暁美ユキ。
わたしの母親だ。
ここに連れてきたのはまどかである。
彼女がいなければは逃げ出してに違いない。
一昨日の晩のことだ。
まどかはわたしの家で寝泊まりを繰り返すようになってから二週間が過ぎたあたりか。
明かりを消し、布団にくるまったまどかの手を取った。
母親に帰省の電話を入れた後のことだ。
「ねぇ。あなたも来て……まどか?」
「え? でもほむらちゃんのお家って札幌なんだよね? それだと……お泊まりだから、おうちの人に迷惑がかかるんじゃない?」
非常識な頼みであることは承知の上だ。
まどかだって気をつかうに違いないのだから。
「大丈夫。もう母には伝えてあるから」
「そうなの? でも……親子水入らずで時間を過ごす方がよくない?」
「あなたが行かないなら、わたしも行かないわ」
「そ、そんなぁ」
こんな馬鹿な頼みをした理由は決して一人で会いに行く勇気がなかったからじゃない。
彼女がわたしの見ていない間に消えてしまうのではという不安があった。
もしまどかが、外出中に蒸発するようなことがあったらと思うと、夜も眠れない。
わたしは知らない。なぜまどかがこの世に現れたのか。
いつ消えてもおかしくない……それどころかまどかのいるこの現実が夢なのかとさえも思えた。
だからそばに置いておきたかった。
そうでなくとも、三が日まで彼女を一人きりにしたくない。
もしまどかが鹿目の家に帰ったとしても、それは今まで通りの家族ではいられない。
「わたしたちもう家族みたいなものだし、構わないわよ。だから一緒に行こう?」
「ほむらちゃん……」
そして今に至る。
母に案内され、屋敷の中をキョロキョロとしていた。
キシキシと音のする廊下。
敷居をまたぐのはおおよそ2年ぶりになるけど、不思議と家のことは覚えていた。
冬になると凍るひょうたん型の池。
二階の怪物に見える黒い大きなシミ。
廊下を進むにつれ、「ああ、こんなだったなぁ」と鮮明になってきた。
「どう?何か思い出した?」
「わからない」
確かに家の間取りや風景は覚えがある。
独特の木造の家屋の匂いや、床の感触さえも……。
しかしどうしてもあの人――白肌の着物の麗人のことだけが思い出せない。
声、姿形、物腰や性質に至る何から何までが、まるで雪野原のように真っ白く塗り固められて。
母はこちらを振り向いて、何も言わず笑いかけてきた。
わたしの影に隠れるように、まどかは小さくなっていた。
「大丈夫よ、まどかちゃん」
どうやら先程の手荒い歓迎にまどかは怯えてしまったようだ。
当然だ。異常な勢いで近寄られあまつさえ体中を触られては溜まったものではない。
理由は不明だがまどかのことをたいそうお気に召したご様子だった。
――まどかが嫌われるよりはいいかしら。そうね。さっきのはこの人なりの歓迎なのかもしれない。
今はただお母さんのことを思い出すことを考えるべきね。
踵を返す母の背中をじっと見つめる。
ほむら(それにしても、実の娘(わたし)よりまどかを先に抱きしめるなんて……)
何畳あるかわからないほど広い居間に通されると、上寿司が皿の上に盛られていた。
五人前はあるだろうか。
彼女は先程とったばかりだからと言って皿や箸を配膳してくれた。
温かい味噌汁も淹れてくれる気遣いはありがたかった。
箸に手を伸ばそうとしたが、まどかを見てその手を止めた。
まだ表の件で震えていたのである。
まあ無理もないだろう。
骨がきしまないばかりに抱きしめては……。
「どうしたの? お腹空いてないのかしら?」
「誰のせいで」と喉元まで出掛かった。
清々しい顔には謝罪の意を示すような態度がまるで感じられない。
とにかくまどかに声をかける。
「いただきましょう?」
「うん…」
躊躇いがちに返事するまどか。
適当なネタを口に運ぶ。
母の言ったとおり、シャリは歯ごたえがあり新鮮な海の幸の味がした。
おいしい。とまどかが口をほころばせた。
「良かった。遠慮せずどんどん食べてちょうだい」
その人も箸を伸ばした。
和服姿で寿司を食べる様はなかなか品があるようで、こうして見れば悪くないと思った。
だとしても、雪を撒き散らしながら、娘の友人に抱きつくとは如何なものか。
「どうしたの? わたしの顔に何かついてる?」
「いえ……」
「それにしても、ほむらちゃんがお友達を連れてくるなんてね……」
「……やっぱり親子水入らずがよかったですよね?」
「そんなことないわ!!」
不自然なぐらい強調する母。
よほどまどかのことが気に入ったのだろうか?
「えっと……」
「いいのよ、わたしが無理矢理誘ったのだから」
助け舟を出す。
まどかが来てくれなければ、旅は成立しなかった。
ここまで来れたのはまどかのおかげだ。
「うふふ……仲がいいのね」
母は薄っすら笑っていた。
なんだかんだで柔和な空気が出来上がっていた。
まどかもいつの間にか震えが止まっている。
あの戯れは、長年会っていなかった緊張を解す為にわざとやったのだろうか。
何にしても母親に会うという目的は達せられた。
いささか物申したい部分もあるが、どこにでもいる普通の女性だと思う。
そういう意味では安心仕切っていた。
久しぶりの我が家も悪くない。
帰る場所が自分にもちゃんとあったんだとはっきりと自覚できたから。
わたしはほっと一息をついて、目の前の寿司に箸を伸ばした。
「ところで一つ聞きたいことがあるの」
「何かしら?」
積もる話もあるのだろう。
なにせ中学に上がってから一度も顔を合わせていないのだから。
母は嬉々としながら二人に質問を投げかけた。
「あなたたち、キスはもうしたのかしら?」
空気が凍る。
まどかはお茶を溢していた。
一方私は自分の聞き違いであることを天に願って問いかける。
「……ごめんなさい。よく聞こえなかったわ。もう一度言ってもらえるかしら?」
ちゃぶ台の上でシャリと離れ離れになった白いイカ。
無残に崩れた寿司を見るでもなく、母は淑女の笑みを漏らしていた。
「キスした?」
なんと満面の笑みだろうか。
いまだかつてこんな笑顔をみたことがない。
いや、そんなことはいい。
キス?
まどかとキスをしたかと聞いているのだろうか?
年頃になると、女の子同士で仲睦まじくなる、……という内容を昔、本で読んだことがある。
その頃のことはおぼろげだが、少々刺激が強かったため、しっかりと残っていた。
正直少しドキドキした。
しかし、それはそれ。
まどかと自分の関係がそのような破廉恥なものであってたまるものか。
いくら母親であり、しかも後ろめたさを感じていたとはいえ、怒りを覚えた。
「わたしたちは女同士なのだけど」
「え……?」
まどかとわたしを交互に見て、口に手を当てていた。
正論を述べた筈なのに驚かれるとは……。
この地方は、年頃になると同性同士がくちづけを交わす風習があっただろうか。
記憶を辿る。
いや、そんな馬鹿げた習慣があってたまるものか!
「あら……違うの? わたしの子だから、てっきり……」
悪びれもなくユキはにこにこしながらお茶をすすっていた。
今ひとつこの人の性格が掴めない。
……ちょっと待って。
「わたしの子だから」と言ったか?
つまり何?
この人はあの本読んだ百合色の世界の住人であるというのか?
母はそういう嗜好がある、あるいはあったということ?
つまりまどかに抱きついたのは……。
「!?」
冗談じゃない。
母親が、女友達に色目を使うなど聞いたことがない。
ひどい頭痛がした。
そして母へ対する罪悪感が薄らいでいく。
まさか母たちの顔を忘れていた原因がよもやこのような理由ではあるまいか?
どうしようもない人だったから、願望叶ってようやく忘れることに成功したのに
海に沈めたはずのパンドラの箱を、わざわざ苦労し探し当て、開いてしまったのだとしたら……。
血の気が引くわたしを見て、まどかは気まずそうに笑っている。
彼女も母の持つ危なげな気配に気づいたのだろう。
泣きたくなった。
他人に、まして今やなくてはならない親友に母の隠しておくべき秘密を知られてしまったとあっては。
『自分は違う!決してあなたのことをそんな目で見たりしないから!』と目でまどかに訴えた。
まどかは、『うん。わかってるよ』とにっこり微笑み返してくれた。
やはりここに来ても、まどかだけが救いだった。
「あらあら、目で会話するほど仲良しさんなのね。昔を思い出すわ……」
恍惚と遠い目をする母。
彼女の頭にはまどかみたいな純粋で愛らしい乙女と、桃色の世界が広がっているのだろうか。
やめて欲しい。
出会って早々、この女性の腹から出てきたことを悔やむことになるとは思いもよらなかった。
あと2年会わなければ、また忘れることが出来るのだろうか?
……多分無理だ。
結局わたしはその場で、怒りを露わにすることはなかった。
数年ぶりに再開した席で事を荒立てたくないし、自分の立ち位置というものが定まってなかったからである。
屈辱とやりきれなさと羞恥に一斉に攻め立てられ、自分でも面白い顔をしていたと思った。
胃が膨らむまで昼食を取り終えると、母はわたしたちを部屋へと案内した。
歩くとキシキシ鳴る階段を登り、障子張りの前までやって来ると妖艶に微笑む。
「それじゃ、若い二人でお楽しみに」
ゆらゆらと左右に揺れながら母はその場を去った。
退散の一句まで余年のないところを見ると、いよいよ残念な人であると認めざるを得ないだろうか。
ご丁寧にぎっちり密着した二組の布団がしかれている。
旅の疲れがどっと押し寄せてきた。
「えへへ、面白いお母さんだね」
まどかの顔は少し引きつっていた。
気を使わせるために連れてきたはずではなかったのに…
「ごめんなさい。気を悪くしないでちょうだい。あと、身の危険を感じたら遠慮なく引っぱたいていいから」
まどかは苦笑いしながら、大丈夫だよと言った。
申し訳ない気持ちと、恥ずかしい気持ちが混じっていた。
自分まであんなだと思われたらどうしようか。
「でもよかったね。ほむらちゃん。あんなに心配してた割に普通にお母さんと話せてるじゃん。羨ましい、やっぱり親子だね」
最後の一言余計だと思わなくもないが、確かにぎこちない雰囲気はなかった。
にしても、自分の母親があんな残念な人だったなんて。
しかし『羨ましい』の一言は胸にくるものがある。
彼女には帰る場所がもうないのだから。
「それに着物が似合ってて、綺麗な人だった。ほむらちゃんも将来あんな美人さんになるんだね」
「見てくれだけならね。黙っていればまともに見えるかしら」
ふふ、とまどかが笑いながら荷物の整理をする。
布団の上で横になった。やはり長旅で疲れたみたい。
本当なら羽田から空の旅を選択すれば時間も経費も安くなる。
それでもわたしには心の準備が必要だった。
腹を痛めて産んでくれたあの人よりも、友人……まどかを選んでしまったことに罪悪感を感じていた。
時間を移動すれば移動するだけまどかへの執着は強くなり、気づけば親の存在など頭から抜け出していたのだ。
咎める人もおらず、自分の罪の意識を知る者はまどか以外にいない。
だけど本当に帰りたくなかった理由は――。
何の便りも寄越さない両親が自分の帰りを待っていると思えなかったからで。
母に再会した時のことがまた頭に浮かんでくる。
嬉々としながらまどかを抱きしめる姿が。
彼女が真っ先に抱きしめたのは自分ではなくまどかだった。
それが気がかりだった。
まだあの人のことがよくわからないから、なんとも言えない。
家を捨てた自分にあの人を責める資格などない。
そんなことはわかっている……。
枕を握りしめ、天井を見上げた。
お母さんが何を考えてるか、全然わからなかった。