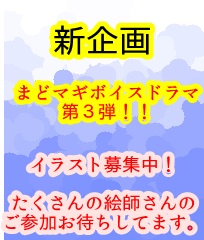ほむらの家族7 戻れない世界で
【第六話 戻れない世界で】
「おかえり、ほむらちゃん」
部屋に戻る、満面の笑みのまどかが待っていた。
まどか……。
まただ、顔を見てるだけで胸が……。息が詰まりそう。
「遅かったね。何かあったの?」
「お茶を汲みに行くときに、いろいろあって」
「そっか。ところでさっき廊下で誰かと話してなかった?」
キュウべぇとの会話が聞こえてたのか。
「父といろいろ話してたから」
「……なんか調子悪そうだけど、大丈夫?」
「ええ」
だめだ……まどかの顔がまともに見れない。
「なんだかさっきから、様子がおかしいよ、ほむらちゃん」
「そ、そう?」
「ちょっとよそよそしいっていうか……昔のほむらちゃんみたい」
昔のわたし……初めて会ったときのことだろうか?
「そういえば、メガネと三つ編みはどうしたの?」
「あれは……家にも馴染めてきたし、もういいかなって」
「残念だなぁ。わたしは好きだったけど。なんていうか守ってあげたくなるような、母性をくすぐられる感じがしてさぁ」
「……いいわよ。別に守ってもらわなくたって」
「うん。 でもちょっと懐かしかったから……」
「そう……」
ループしてるときは、まどかに全部伝えられたら、どれだけいいだろうと思っていた。
弱かった頃のわたしのことも含めて、全部、全部わたしのことを知ってもらえたらって。
でも、いざ知られてしまうと……。
なんだか、今のわたしが背伸びしているのを見透かされているようだ……。
「もうあの頃みたいに、わたしを頼ったり、すがってくれてくれないのかな?」
「頼ってるじゃない。こうやって実家まで連れ回して迷惑をかけて」
「あなたがいなければ、両親に会うことなんてできなかった」
「……よかった」
まどかは、本当に嬉しそうだった。
でも、わたしは心から笑うことはできなかった。
──この笑顔が憎いの?
ありえない。
大好きで、何より大切で……。
なのに、まともに見ることができないなんて。
「やっぱり、何かあったの?」
「父とちょっとね。大丈夫よ。[w1]それよりお茶でも飲みましょう」
ズズ……。
一度抱いた羨望が憎しみに変わることは珍しいことじゃない。
――嫌いな人を好きになるにはどうすればいい?
『自分を騙すことだ』
“騙す”とはどうすればいいのだろう。
少なくともまどかのことは好きだと思っている。
まどかがいれば他になにもいらない。
逆にいなくなれば自分は生きていけないと思うくらいだ
これ以上ないというほど大切に思っている相手を、どう好きになれというのだろうか?
「どうしたの?」
「い、いえ……」
口が避けても言えるはずがない。
「もぉ、今日のほむらちゃんは何かおかしいよ」
まどかはこっちに寄ってきた。
――い、いや…近寄らないで。
「そんなほむらちゃんにはこうだぁ!」
「いやっ!」
その手を振り払い、思わず左へ身をかわした。
「はぁっ……はぁっ……あ……まどか…ごめんなさい」
一方まどかの身体は宙へ浮き、畳の上に叩きつけられてしまった。
「ひどいよ~」
涙目でこちらを見つめるまどか。
「でも……その、母や父に見つかると嫌というか」
「そ、そうだね。ごめん。私が悪かったよ」
とは言え、『いやっ!』などとまどかを拒否した理由の説明にはならなかった。
身体がとっさに動いてしまったのだ。
まどかに抱きしめられると思うと、身体が熱くなり、思わず手を振り払って……。
なんてことをしてしまったのだろう。
まどかを見ると体育座りでなんだかしょんぼりしている。
ああ、そんなあから様に落ち込まないで。
あなたは悪くないの。
いつも通り甘えてくれたのよね。 わかってる、わかってるわ。
私はそれを拒む気はないし、甘えてくれるのだって悪い気はしていないの。
まどかに頼られてるんだって、思うとうれしくって…ちょっと照れくさいけれど嫌じゃないの。
嫌じゃないはずなのに……。
まどかが恨めしげにこちらを見つめている。
「わたしはあなたの恋人じゃないのよ……」
「わかってるよ。 わかってるけど……」
恋人?
そうか。その手があったか!
これ以上ないというほど大切に思っている相手を、どう好きになればいいか。
幸いわたしにはその素養がある。
残念なお母さんから受け継いだ……かどうかは知らないけど。
でもまどかを手放すぐらいなら、悪魔に魂を売ることも厭わない。
嫌いになる前に、愛してしまえばいいのだ!
「ねえ。まどかは母に出会ったとき、散々な目にあったわよね? そのとき正直どう思った?」
どうしたの急に? という顔をするまどか。
「う~ん。びっくりしたかな。なんとなくほむらちゃんのお母さんて落ち着いてそうな人をイメージしてたから」
「母に対する印象ではなくて、その……抱きしめられたときにどう感じた?」
「え、ぎゅってされたこと? う~ん覚えてないよ。なんか頭が真っ白になっちゃって」
「憶えていない……そう。そうよね」
でも記憶が正しければ居間でのまどかは少し尻込みしていたと思う。
少なからず母に苦手意識をもっているようだった。
いきなり抱きつかれれば無理もない。
「もし私が…」
「……何?」
もしわたしがお母さんと同じことをしたら……と、しかし言葉が続かない。
いざ言葉にするのが恥ずかしくて。
それにもし勘違いされて嫌われでもしたら明日から生きていけない。
やはり無理にお母さんのようになろうとしても、うまくいかないのか。
思い悩んでいると、今度はまどかが照れくさそうにこちらみているのに気が付いた。
「ねえ、ほむらちゃんは……その……お母さんみたいに、女の子が好きになったりしたことはないの?」
「……」
絶句した。
自分の考えを先読みされたような気がして。
「もしかしたら、私もそういう目に遭っちゃうのかなって」
少し怒りはらませたを笑顔を”みせながら”まどかのほっぺたをつねった。
「い、いひゃいよ、ほむらひゃん」
相変わらずほっぺたは柔らかく伸縮に富んでいた。ほんとよく伸びる。
「ふふふ、面白い顔」
「や、やめへよ」
あんまりやりすぎてもかわいそうなので、適度なところで手を放してあげた。
涙目でほっぺを右手でなでながら見つめる片目には恨みが籠っていた。
「も、もう、ひどいんじゃないかな?」
「あら、人を変態扱いしておいて自分だけ被害者ぶるのはどうかと思うわよ」
言えない。
本当は自分が何を考えていたのか。
「別にほむらちゃんのお母さんが変態だとは、私思わないよ」
「え…あれが?」
まどかはお母さんを軽蔑したわけではなかったのか。
それでも苦手そうに、距離を置いているように見えたが……。
実際はよくわからない。
「もし、私が母と同じような人間で、だれかれ構わず抱き着くようなことがあったらどう?」
「え~、嫌だなぁ~~。そんなほむらちゃんは見たくないよ」
まどかは笑いながら言うのだった。
やっぱり、嫌か。
まどかだって、お母さんのような奇特な性癖はよく思わないだろう。
「でも、誰かを好きになって……そうなったらさみしいかな」
まどかは独り言を言うようにひっそりとつぶやいた。
床を見つめるその目はどこか寂しそうで。
わたしはそれを聞き逃さなかった。
何故か平静を装っていたが身体のそこらじゅうが熱くなった。
「大丈夫よ」
すると物憂げなまどかの瞳がわたしをとらえる。
「えへへ。そうだよね。どこにも行ったりしないよね……」
――まただ。
心臓を鷲づかみにされたような胸が痛い。
なぜまどかに見られるだけでこんなにも苦しいのか。
それでも平静を装って、まどかの話に耳を傾けた。
「私ね、不安になっちゃったんだ。もしかしたらほむらちゃんがこのまま実家で暮らすんじゃないかって。そしたら私、ほむらちゃんにどんな言葉をかけてあげればいいんだろうなって……。ねえ、ほむらちゃん。ほむらちゃんはこのままお家に残りたいと思ってるのかな? って……私が聞くのはなんだか卑怯だよね……ごめんね」
まどかは謝ると笑顔をこちらに向けてきた。
無理に笑っているのがよくわかって痛々しい。
卑屈な自分を恥じているようにも見えるが、不安で震えているのがわかった。
気が付くと後ろからまどかの脇腹から腕をまわしていた。
――まどか。
自然と身体が動いた。
寄る辺ないまどかの様子を見ていると、まるで自分が身が削られるようで。
「久しぶりだね、ほむらちゃんから抱きしめてくれたの。嬉しいな」
言葉とは裏腹に、まどかの声色には申し訳なさが含まれていた。
少しでもまどかを安心させてあげたい。
「私……もう帰るつもりはないわ。多分来年はもう帰らない」
ただずっとまどかの側にいるということが伝えたかった。
家族と関係を断つことをまどかが望むとは思えないが、それぐらいしかまどかを守る言葉が思い浮かばなかった。
出任せに出た言葉ではない。
本当に帰るつもりはない。
ここにわたしはいるべきでない。
たとえ何かを思い出せたとしても、虚しいだけだから。
何よりこの場所にいると、まどかのこと嫌いになってしまいそうで怖くてたまらない。
惨めな気持ちが、自分とまどかを引き裂こうとするのが恐ろしい。
そんな危険な場所にいる理由がない。
それにお母さんはわたしと距離を置いている気がする。
なぜかはよくわからないけど、あの人が遠く感じる。
こんな広い家に閉じこもって、毎日家事に追われているのは、誰のせいか。
もしかして、わたしは……。
……だからこの家を?
それは無意識に避けていた答えだった。
お母さんに疎まれている。
「わたし、もう帰らないから。心配しないで」
涙が出そうになった。
もう、何もかも遠い人なのに、その人から嫌われているかもと考えるだけでどうして……。
「……そっか」
反論しない?
まどかなら絶対に認めないと思ったのに。
ぽつんという音がしたと思うと、ほむらの手に水滴のようなものが次々に落ちてきた。
「泣いているの?まどか」
「ごめん、ごめんね。本当は怒って、そんなこというほむらちゃんを窘めて……。
だけど……やっぱり私にはほむらちゃんしかいないから。
もしほむらちゃんが誰かのことを好きになって、どこかにいっちゃったら……私どうしていいかわかんなくて……嫌な子だよ」
目頭が熱くなった。
――泣かないで。
大丈夫だから。
あなたは嫌な子なんかじゃない。
まどかのことが羨ましいと思っていたけれど、どうかしていたんだ。
まどかの境遇というのは誰もがうらやましがるようなものではない。
世界から取り残され、孤島に一人ぽつんと置き去りにされた存在。

くぅるさん作
その隣にただ自分のような存在がただいるだけで。
それでもまどかは必要としているのだ。
どこかに行ってしまうのを、何より恐れて。
一人きりになるのが怖くて、卑怯だと知りながらも、こうしてわたしを繋ぎとめたくて。
「大丈夫よ、私はどこにも行かないわ」
するとまどかはの、胸に顔を押し当ててきた。
ふわふわの髪が鼻のあたりを掠めてくすぐったくて……。
鼻腔に広がる甘い匂いが、ひどく落ち着かない気分にさせた。
「あ……」
いつもまどかにされていることなのに、今日はなぜか顔に熱がのぼっていく。尋常でないくらいに。
普段はどうしていたのだろう。
このままぎゅっと抱きしめればよかったんだろうか?
腕を、まどかの背中に回した。
そういえば、いつもは髪をなでてから背中をさすっていたような気がする。
慌てて髪をなでるが、その手つきはどこかぎこちない。
「どうしたの、なんかほむらちゃん焦ってるみたい」
自分でもわからない。
いつも通りまどかが甘えているだけなのに、何が違うというのだろうか。
そのとき、こちらを見ずに重たい声でまどかは言った。
「ねえ、ほむらちゃんは何に気付いたの? 教えて」
「気付いたって、何のこと?」
「夕食のとき、すぐに席を立ったでしょ? その時ほむらちゃんの顔が青ざめてた」
『夕食』という一言で、表情が凍った。
まさか、まどかはあのことに気付いてしまったのか?
「本当は聞くつもりなかったんだけど、きっと家族のことで何か思い当たることがあったんだよね」
「い、いえ……」
どうやら真相はわかっていないみたいだ。
言えない。
きっと本当のことを言えばまどかは悲しむに違いない。
家族の記憶が、書き換わったこと。
お人よしの彼女にいらぬ重荷を背負わせたくない。
黙っていると、まどかの表情に暗い影が刺した。
「私だってほむらちゃんの力になりたいよ……それとも私じゃだめなのかな」
「違う、違うのまどか。確かに私はあなたに隠し事をしているわ。だけどこれはあなた自身にも関わりがあることで、今は話すことができないのよっ!」
「そんなっ! なおさら気になるよ」
正直に話すべきなのか。
今までまどかに隠し事をしてきていい思いをした例がない。
しかしこんなことまどかが知るべきではない。
この件にまどかが関わりがないとも言い切れないからだ。
「些細なことだから本当……気にしないで。私が慌ててることとは関係ないから」
もう一度まどかの目を見る。
「信じて……」
まどかの手を握った。
「ほむらちゃん……」
不安気な瞳の色に、いつもの輝きが戻った。
「……もう。ほむらちゃんは、昔からそうやって人の心配ばかり」
まどかの腕が、背中にかかる。
ほむらの肩にまどかの顔が乗りかかって、頬と頬が触れ合う。
柔らかい感触が、再び胸を高揚させた。
やっぱり、まどかといると落ち着かない。
「私強くなるから。ほむらちゃんに頼られるぐらいに。ほむらちゃんが気兼ねなくなんでも話をしてくれるぐらいに、私……なってみせるから」
「ありがとう……」
――私の言葉の意味を汲み取ってくれて。
キュウべぇに騙され、ほむらの言葉に耳を貸さなかった頃のまどかとは違う。
まどかには自分が伝えたいことが伝わる。
もう昔のような関係ではないのだ。
二人でどこまでも一緒に生きていきたいと思った。
本当の家族とは、もう元に戻れないこの世界で。
――だけど……なんなんだろう。
まどかに触れてるだけで、切なくて…もどかしくてたまらないこの気持ちは。
羨望でも、劣等感でもない……顔が熱くなるような不思議な高揚感が収まらない。