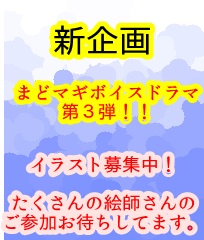ほむらの家族3話 『初恋』
魔法少女まどか☆マギカ ~ほむらの家族~
【第三話 初恋】
ここは……?
そうだ、確か実家に帰ってきたんだった。
疲れのせいで、瞼も身体も重たくて動く気になれなかった。
まどかの匂いがした。
いつもの調子で甘えてきたのだろうか?
案の定目を開けると、まどかに抱きしめられるように寝ていた。
嬉しくもあったが、ユキに見つかったら後で何を言われるかわからない。
暁美ユキ……。
変態が自分の母親だったのか。
嫌がるまどかに節操無くまとわりつく子泣きじじいに見えた。
窓を見ると、空はにわかに暗くなりかけていた。
「結局、思い出せないのよね」
会えば昔の記憶が綺麗に一本の糸に繋がると思っていたが、実際は違った。
あの人が母親だったという実感がまるでない。
自分の母と認めたくない気持ちが邪魔をしているのかもしれないが……。
よほどあの人のことを忘れたかったのだろうか。
あるいはわたしが薄情だったせいか。
ただ思い出せない原因が、あの母親にもあると思うと肩の荷が下りた。
なんにしても、少しでも思い出さなくちゃ。
あまり思い出してもいいことはない気がするけど、この際気にしても仕方ないわよね。
そうね。あんなでも私のお母さんなんだもの。
家の中をふらつくことにした。
なぜか家の構造や間取りだけははっきりとおぼえていた。
初めてこの家に来たのは、小学生にあがってしばらくたってからだっただろうか。
それまでは母方の祖父母と暮らしていたが、祖父も祖母も優しくしてくれた気がする。
正月には餅をついたり、電車で動物園に出かけたり、祖父の趣味に乗じて渓流に釣りに連れて行ってもらったこともある。
病院暮らしを除けばそれは楽しい時間だった。
どうして、お母さんたちのことだけ思いだせないんだろう……。
障子張りの廊下をギシギシと音をたてながら歩くと、下り階段の直ぐ側に大きな染みを見つけた。
黒く淀んだ壁は、この家にきた時には既にあったものだ。
一階のトイレに行くにはこの前を通らなくてはならない。
こんなものが怖かったなんて。不思議ね。
時間をおけばなんてことはない。
夜中に一人で行くには、かなり時間を要した気がする。
つまり、それまではお母さんかお父さんに付き添ってもらったんだ。
夜中に起こされ、二人共苦笑したに違いない。
でも……どうしてこんなことばかり覚えているんだろう。
家のことは覚えているのに二人のことが絡むと、どうしても思い出せない。
一階に降りるとちょうどお母さんが膝をつきながら床の掃除をしているところだった。
この広い家を一人で管理しているのかしら。
三世帯が広々と暮らせるぐらいの土地と部屋がある。
わたしの方から母の隣に寄っても無言のまま掃除を続けていた。
仕方なく話しかけた。
「何か手伝うことはない? 一人では大変でしょ?」
「いつもやっていることだからね」
床を磨く母は、ただ真摯だった。
広々とした家の庭を見渡す。
「人を雇ってもいいような気がするのだけれど」
「ふふ。そうかもしれないわね。でも私が好きでやってることだしお金がかかるわ」
未だに母の性格が真面目なんだか、尖ってるのかわからない。
ふざけているように見えて、やることはしっかりこなすタイプなのか?
面を食らっているが母は無言で掃除を続けていた。
久しぶりに帰ってきたというのに、何か話すことはないの?
普段は何を食べているかとか、学校の勉強はどうだとか、聞きたいことは?
もちろん聞かれても答えられないこともある……魔法少女のこと。
胸の奥が、もやもやとしてきた。
しばらく無言で立ち尽くしていると、この人の頭の中に『私』という存在はとうに消えてしまったのだろうかと思えてきた。
それは長い間家を離れていたせいなのか……。
あるいはもともと……。
長い間電話がなかったことが引っかかる。
……もし昔の自分のままこの状況にいたらどうだろう。
今はまどかが支えとなっているから、表情一つ変えずに立っていられるが……
身体も心も弱かったころ、自分は耐えられただろうか。
むかしわたしはこの人とどう接していたのだろう。
このままいるのはなんだか惨めな気がしたので、無言でその場を離れた。
居間に腰を据えて廊下で雑巾を握る母の姿を見つめた。
根は真面目な人間なのかもしれない。
先程はおどけていたが、普段はあのように家事をこなしているだけで。
これだけ広い家を一人きりで掃除するのは楽なことじゃない。
家政婦だって雇わないようだし。
父と二人きりで住むには広すぎる家だ。
分はここにいても良かったはずなのに……
なぜこの家を飛び出さなければならなかったのか。
黙々と掃除をする母のことも気になった。
うまくお金を回せばもっと楽な生活ができるはずなのに……
本当はお金がないのだろうか?
わたしが単身で遠くの学校に通っていることが家計にひびいているのか。
そのせいで母に苦労を強いているのだろうか。
飛び出した理由はわからないが、そういうことなら何かできることをしたい。
外はすっかり暗くなっていた。
雪はもうやんでいたので視界だけはまともに確保できる。
だから雪かきをすることにした。
倉から取り出したスコップを両手に白くて重い塊を掻き分けていく。
息をすると度の入っていないメガネが曇った。
知ってはいたがたまりにたまった豪雪は信じられないぐらいの重量がある。
無理に大量の雪をかきあげようものなら、腰や腕に多大な負担がかかるので、自分の力に合った一定量の雪をスコップですくい取ることがコツだった。
それでも腰に負担がかかるので、自然と汗が滲んだ。
極寒の氷下にいたとしても、厚着でこれだけの作業をすれば自然と身体は熱くなる。
足元付近の雪をかき分け一息つく。
「まだこんなにたくさん残ってるのね……」
十五分ほどかけて行った作業は、全体の十分の一にも満たない。
ここまで広いとついやる気を失ってしまう。
爆薬や魔法で吹き飛ばしてしまおうかと思ったが、家ごと飛ばしかねなかった。
「頑張ってるね!」
しばらく雪掻きをつづけていると、防寒着を来たまどかが現れた。
「まどか?」
「私一度雪かきやってみたかったんだ。手伝うよ」
うぇひひ、と生き生きとした笑顔を見せるまどか。
お礼の言葉を言うと、手元のスコップを渡して倉から柄のついていないプラスチック製の雪かきを持ちだした。
正直二人でも終わる気がしないが出来る限りの手を尽くして雪を掻きわけた。
「何が楽しくて二人だけでこんな無駄に広い家に住んでるのかしらね」
「ほむらちゃん……もしかして見滝原に帰りたくなった?」
「別に。ただ母もいつまでも体が持つかわからないのに、こんな暮らしを続けるのかって」
「ふふ、お母さんのこと心配なんだね」
……心配なのかしら?
全く何も思い出せないあの人のことを、わたしはどこまで母だと思ってるんだろう。
「わっ…重いよ。全然上がらない」
雪をスコップでぎこちなく持ち上げるまどかの姿を遠くから眺めていた。
いきなり壁のように立ちはだかっているところに先端を突き立てている。
あれじゃ重くて引き抜けないだろう。
案の定、必死になってスコップを引っぱっている。
まどかのそばまで駆け寄り、一緒に取っ手を握った。
「ほむらちゃん。ごめん、引っ張ってもらっていいかな?」
涙目になりながら訴えるまどか。
頷くと、案外簡単に抜けた。
「す、すごい。すぽってぬけたね。私が引いても全然抜けなかったのに」
「まあ、こういうのにはコツがいるのよ。テコの原理ね」
「そうなんだ。さすがだなぁ」
まあ嘘だけど。
まどかより格段に力強いわけでもなければ、物理的な力を応用する術を極めているわけでもない。
ソウルジェムを密かに握りしめながら、微笑んだ。
秘密はまどかには話さないことにしておくとしよう。
尊敬の眼差しを味わっていたい。
数時間後。
二人で雪かきを続けるうちに気がつけと表の通り道にはほとんど雪がなくなっていた。
「やった!終わったね」
「お疲れ様、手伝ってくれてありがとう。まどか」
「うん。ねえちょっとこれで遊んでいこうよ」
庭の隅に雪が積み上げられられ、巨大な山を形成していた。
エベレストがわたしたちの前に立ちはだかっている。
一応邪魔にならないように端のほうに積んだつもりだが、その存在感は尋常ではない。
春になるまで残り続けそうな生命力を感じた。
「みてて、ほむらちゃん」
まどかがその雪山の上を駆け上がっていく。
雪で遊びたくてうずうずしてたんだ。
あちらではこんな大量の雪を目にすることはないし。
よ、よ、よ、とへっぴり腰になり慎重にゆっくりとすすんで行く姿が可愛い。
「芋虫みたいね」
「ちょっと、今頑張ってるんだから変なこと言わないでよっ!」
集中力がこちらに削がれると、まどかはズルズルと滑り落ちてしまった。
げふんっという声をきくと、わたしはクスクスと笑うのだった。
まどかは恨めしげにわたしを睨みながら反論する。
「もう、ひどいよ。ほむらちゃんは登れるの?」
子供の頃から雪には慣れていた。
病院での生活も長かったけれど、まどかよりは雪との付き合いが長い。
これぐらい余裕だろう。
「もちろん」と頷いてわたしはエベレストに立ち向かった。
滑らないように雪の柔らかい部分を見つけてそこを足場にする。
そして足でゆっくり固め、それを繰り返しながら上へ上へと進んでいく。
両手を使いながら、わたしは軽々とエベレストの頂上までたどりつくことができた。
雪国育ちの子供にとっては朝飯前だ。
下にいるまどかが感心したように、拍手している。
塀の高さぐらいはあるから、住宅街が一望できた。
いつの間にかまた雪が降り出していた。
また明日も雪かきしなくちゃいけないわね。
わたしはため息を漏らすと、雪を背景にした暗がりの街並みがとても幻想的なことに気がついた。
銀色の世界にぽつんとわたし一人が降り立ったような気分。
なんだか物寂しくて、切なくなった。
腰を下ろして、ほら。と下に向かって手を伸ばす。
「早く登って来なさい」
どんな時もわたしのそばにいると言ってくれたまどか。
彼女に向かって向けて呼びかける。
まどかは慎重に慎重にわたしが作った足場を登っていく。
その様子を優しく見つめながら、ぼんやりと思った。
こんなところまで一緒にこれたんだ。
見滝原から遠く離れた実家。
はるか北の遠方の地まで、親友と手を取り……。
同じ時を繰り返し、失うことも別れを繰り返すことも、憎むことも、涙を流すこともなくなり、ただ誰よりも一緒にいて欲しかった人と隣に迎えることができる。
まどかが伸ばした腕を、固く握りしめた。
全神経を集中して力を右手に注ぐ。
もう少し……肩に力をいれ、思いっきりまどかを引き上げた。
するとまどかの身体が宙に浮き上がり、わたしは慌ててその身体を抱き寄せる。
バランスを崩して転んでしまい、背中と尻が打ちつけられた。
が、なんとか山頂で持ちこたえたようだ。
仰向けになって、天を見上げる格好になっている。
空から降ってくる雪が虚ろに見えた。
そこにまどかの心配そうな顔が視界にスライドしてきた。
「大丈夫よ」わたしは透けるような声で言う。
――あっ……。

さくらさん 作
白い吐息が振りかかる距離に彼女の顔があった。
心配そうなまどかの顔が笑顔に変わり、その輝きがまるでわたしの胸の奥へ溶けていくような感覚を覚えた。
凍てつく氷を溶かすような温もりで、冷たいはずの外気が、まるでそこだけ別の空間に包まれているような気がして……。
鼻が凍って嗅覚が死んでいたはずなのに、まどかの髪の匂いが漂ってくる。
わたしの瞳には降り積もっていく雪も、曇天の濁りも映っていなかった。
あるのは一点の曇のないまどかの笑顔だけで……。
光が眩しいせいか、見ていると目がやられてしまいそうなぐらいで、顔も急に熱くなってきた。
今まで感じたことのない熱くて切ない熱情にわたしは襲われた。
わたしが息をするのを忘れていると気づいたとき、そっとまどかから視線を外した。
きょとんとした顔で、わたしを見つめるまどか。
「その、どいてもらってもいいかしら?」
「ああ、ごめん」と言いながらいそいそと謝りながらまどかは離れていった。
まどか身体が離れると切なさの槍が再び胸をえぐるようにつき刺してくる。
どうしたというのだろうか。
まどかは近くにいて、手も握れる距離にいるというのに、何かもどかしい気持ちになる。
「うわあ、絶景だね!」
感嘆の声を上げるまどか。
白銀の町並みを、嬉々としながら見下ろす。
まともに顔が見れそうになくってぼんやりと遠くを見やる。
わたしはぎこちなく「そうね」と答えた。
同じ景色を見ているはずなのに、不思議だ。
さっきまでと全然違うものを見ている気がするのはなぜだろう。
いや、景色を見ているのではない。
わたしが気になっているのは、雪景色に映える町並みなどではなかった。
あどけなくて輝かしい瞳と、地べたを見比べているのだ。
まどかがわたしの手を握ってきた。
「えっ?」
ドクン……。
――鼓動が……胸が……今…。
「ありがとう。私なんか連れてきてくれて。本当はほむらちゃん一人で家族水入らずにしてあがったのに。心配してくれたんだよね。私が家に帰れないから……」
動悸が激しいリズムへと変わる。
変だ。
何が起きているのか全くわからなくなった。
手を握られ、笑顔を向けられ、まるで転校初日のあの時のようだ。落ち着かない。
まどかの側から一刻も離れたいという気持ちと、もっと触れていたいという気持ちが同居して、ただただ苦しかった。
今までまどかと一緒にいてこんな気持ちになったことはないというのに。
思考もおぼつかない。
何が起きているというのだろうか。
息を整えて、まどかの目を見る。
「ま、まどかがいなかったら、私はここにいなかったわ。こうして手を引いてくれなければ、辿りつけなかったもの」
実際まどかがいなければ、青森から十八切符でも購入して観光に出ていたと思う。
でもわたしにとって今はそんなことどうでもよかった。
なんだか顔が熱くて、どうにかなってしまいそうなわたしをまどかに見られるのがなんとなく恥ずかしい。
逃げ出したい気持ちが先走り、まどかの手をほどいた。
「私先に降りるから、あなたも早く降りてきなさい」
「え、もう降りちゃうの?」
まどかに肩を触れられると、まるで氷を背中に突っ込まれたかのような戦慄が走った。
「ほむらちゃん?」
わたしはまどかの呼びかけには答えず、あっさりと雪山を降りる態勢になった。
うつむきながら雪の手の塊に手をかける。
下を見ないようにして適当な足場を見つけ下るのだが、どうしても手が震えてしまった。
どうしたんだろ、私。
まどかが心配そうな目でこちらを見つめていた。
それだけで胸が苦しくて、切ない気持ちが沸き上がってくる。
とにかく落ち着かない。
早く降りなければ…どうにかなってしまいそうだ。
しかし、焦ったせいかわたしは足を滑らして、身体が宙に浮いてしまった。
わたしを呼ぶ声がエベレストの上から響いた。
全身を防寒着で覆っていたので、落下した痛みは殆ど無かった。
ちょっと膝をすりむいている気がするが、背中をぶつけたぐらいでなんとかなった。
わたしが立ち上がろうとすると、すぐ後ろから手が添えられた。
「立てるか?」
その人はまどかでもお母さんでもなかった。
黒いコートを着用したサラリーマン風の男がこちらの手を差し伸べ立っていた。
背丈はそれほど高くないように思える。お母さんと同じぐらいではないか。
ほとんどあどけない顔を残したまま大人になったという感じで、まだ随分と若く見えた。
特に太っても痩せてもいないという印象。
「ほむら。おかえりなさい」
男は優しくわたしの手をとった。
もしかしてこの人が……と、わたしは思った。
すぐにまどかが滑り台から降りるように降りてきた。
「こんばんわ。君がほむらの友達か。遠いところよく来てくれたね。自分の家だと思ってゆっくりしてくれ」
「ありがとうございます。えっと、ほむらちゃんのお父さん?」
いかにもと笑みを漏らす。
わたしが想像していたよりもずっと柔らかい物腰。爽やかな青年といった印象だった。
母のような変人であることを覚悟していたが……
この人が私の。
父、暁美敏和なのか。
優しそうな人だった。
「なんだそんなに睨んで? 俺の顔に何かついているか?」
いけない。必要以上に怖い顔をしていたようだ。
わたしは息を飲み込んで、気分を落ち着かせた。
今一度冷静になって思考を始めた。
母の前ではついつい今の感じで話してしまったけど、父はどうなんだろう?
余計な疑いを持たれることを考えると、昔のままに戻ったほうがいいかもしれない。
しかし目の前にはまどかがいる。
まどかの前であの弱かった頃のわたしを見せるのは嫌だった。
「あ、あの……私……」
狼狽してうまく言葉にならない。
父が頭に手を置いて、ゆっくりと髪をなでる。
あ…と、わたしが口を開けたまま父の笑顔を見た。
「大きくなったな、ほむら 」
懐かしいこの感覚。
「あっ……」

むむむのムさん 作
そうだ。私憶えている。
この人に撫でられるのが好きだった自分。
顔の記憶が、未だにつながらないけれど、この感覚……。
今日初めて実感した。
ここがわたしの家であるということを。
帰ってきたということを。
「わたし……帰ってきたんだね……お父さんっ!」
わたしの目からぼろぼろと水滴がこぼれ落ちた。
「泣くほどのことか? まあ一年と半年ぶりで、もうずいぶんほむらには会っていなかったもんな」
たった一年半。
父にとってはその程度の時間だったらしい。
わたしにとっては気の遠くなるような年月だった。
まどかにこれがわたしの父だと誇らしげに言ってやろうと思ったが、まどかの方を見ると涙を堪えているのがわかった。
『よかったねほむらちゃん』とまどかが目で訴えてくる。
父の知らない事情を知っているだけにまどかはここで泣くわけにはいかないのだ。
後でたくさんお礼を言おう。
まどかのおかげで、二度と帰るつもりのない場所へと辿りついたのだから。
ありがとう、まどか。あなたのおかげで、私は帰ってくることができたよ。