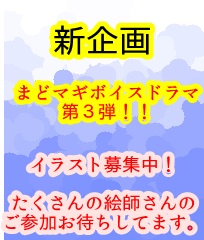ほむらの家族2話二つの家族
魔法少女まどか☆マギカ ~ほむらの家族~
【第二話 二つの家族】
荷物の整理を終えると、布団の上で寝息をたてているほむらちゃんがいた。
「ほむらちゃん、もう寝ちゃったの?」
呼びかけてみたけど返事がなかった。
ちょっと目を離した隙に……。
長旅と、お母さんにあったせいで疲れちゃったんだろうなぁ。昨日の夜も寝てないみたいだったし。
せっかく雪が降っているからお外に遊びに行こうと思ったんだけど……。
窓から見える雪が、ゆらゆら揺れるように舞うのが、見てて面白かった。
見滝原でもこれだけの積もったら、雪遊びができて楽しいだろうな。
振り返ってぐっすり眠っているほむらちゃんを見つめた。
「よっぽど疲れてたんだね……」
そりゃそうだよね。顔も思い出せないお母さんたちと会うんだから。
長くて三つ編みされた髪の脚が敷き布団から畳にはみ出していた。
赤い縁のメガネを付けたままぐっすりなっていたので、それをゆっくりとはずしてあげる。
お疲れ様。ほむらちゃん。
お母さんに会えてよかったね。
遊びに帰ってきたわけじゃない。
過去の自分を取り戻そうと、一歩踏み出したんだ。
道中、震えているの姿を何度も目にした。
わたしには、その手を握ることしかできなかった……。
「はぁ……」
ため息をついた後、部屋を見渡した。
何年も主が留守にしていた割には、整然と片付けられている。
畳敷きの部屋に古い樫の木で出来た幅の広い机が備えられていた。
その上には小学校の教科書やら、小説やらが立てかけてある。
へぇ、たくさん本読んでたんだなぁ。
わたしの旅の目的の一つは、昔のほむらちゃんのことを知ること。
これまで、何度も時間移動を繰り返してきたことや、その間にあったことは知っている。
けれど、見滝原に来る前のことをほとんど知らなかった。
初めてあった時のほむらちゃんのことは覚えているけれど、なるほど家で本を読んだりしてじっとしていることが多かったのかも知れない。
机の上にあるノートの束が気になって、立ち上がった。
ぐっすり眠っているほむらちゃんを見て、こっそりとノートに手を伸ばしてみる。
わ……きれいな字。板書もきっちりしてるなぁ。
やっぱり小さいころからしっかりしてたんだ。
もっとむかしのほむらちゃんのことが知りたい。
そんな好奇心から机の引き出しを引いてみると、たいへんなものが現れた。
「わわわ……ど、どうしよう」
通知表だ。
さすがに、黙って見ちゃ怒られる……よね?
で、でも気になるなぁ。
後ろを振り返ってみると、まだぐっすり眠っていて、ぴくりとも動かない。
唾をごくり、と飲んでわたしは薄い紙に手を伸ばした。
「うわぁ5ばっかだよ……さすがほむらちゃん」
国語はもちろん、算数も、理科も、社会も。
唯一昔のほむらちゃんが苦手そうな体育ですら、3がついていた。
わたしとちがって、むかしから出来る子だったんだ。
ついでにコメント欄も読んでみよう。
「ええっと、暁美さんは明朗で自分の意見を率直に表現することができます。ただ、ものの言い方が少々厳しいことがあるので、お友達とお話しするときは注意しましょう……か」
ほむらちゃんの近くに体育座りした。
寝息が聞こえてくる。
「お母さん、綺麗な人だったね。ほむらちゃんもいつかあんな風になるのかな」
未来のほむらちゃんの姿を想像してみた。
大人になったほむらちゃんは、今よりもずっと綺麗になっていて……。
……だけど。
「未来……かぁ」
今は考えるのやめとこ。
わたしはほむらちゃんのお母さんのことを思い出した。
ほむらちゃんの前では口に出さなかったけど、あの人のことが少し怖かった。
何がどうして怖いのかを言葉にすることはできないけれど、強いていうなら自分よりとても大きな存在がいて、萎縮してしまうような感じ。
ほんの一瞬だけど、それを見てしまった。
笑っているのに、底冷えするような冷たい、黒い瞳。
この世を恨んでいる眼だ。
それが、まるで……。
まるで……。
トン、トントントン……。
「っ!」
足音!? 近づいてくる。
瞬間、ほむらちゃんのそばに駆け寄った。
どうしよう……。
胸を抑えていると、障子戸は開いた。
「ごめんなさい、今大丈夫かしら?」
顔を出したのは言うまでもなく、ほむらちゃんのお母さんだった。
「わ、私は大丈夫です」
わたしが笑顔を作って答えると、何故か無性に嬉しそうににっこりと笑っていた。
「そう」
「ほむらちゃんは、この通りぐっすりですけど」
「疲れが溜まってたのね。無理もないわ」
見滝原から、ここまで半日以上の時間がかかった。
だけどほむらちゃんの疲労は、ただの旅の疲れじゃない。
そのことを、おばさんも気付いていんじゃないかって思った。
「少しまどかちゃんお話がしたいのだけれど、いいかしら?」
「えっ。わたしと……ですか?」
なんで? と聞きたそうな顔をしたせいか、おばさんは付け足すように言った。
「学校でのほむらの様子を聞かせて欲しいと思って」
「うっ、わかりました……」
やっぱりわたしはこの人のことが苦手だ。
ギシギシと階段の音を聞きながら階下に下る。
木造で相当年季の入ったお家だった。
「ほむらから聞いているかもしれないけれど、この家はほむらのお父さんのものでね、祖父の代からあるみたいだからちょっと古くなってるの。床が抜けることはないと思うけれど、階段は暗いから気をつけてね」
「だいじょうぶです」
古いお家には慣れてないけど、なんだか旅館に来たみたいで楽しかった。
「お祖父さんは一緒に住んでるんですか?」
「いいえ。市のお偉いさんだったけれど、もう亡くなってしまったの。跡を追うようにして、お義母様も。ほむらは一度も会ったことがないの」
「そうなんだ……」
「まどかちゃんが気にすることないわよ。会ったことないひとに、何か情があるとも思えない。あの子もそんなこと気にしてないでしょう」
わたしにはよくわかんない。
おじいちゃんも、おばあちゃんもまだ両方生きているけど、始めから会えなかったら、何も感じなかったのかな……。
……そっか。
わたしは、もしおじいちゃんたちが死んだとしても、お線香をあげることもできないんだ。
それどころか、亡くなっても、それを知ることも
鹿目の家に帰れないっていうのはそういうことだから……。
おばさんに居間に案内された。
梅昆布茶をもらって、向い合って座る。
膝が……痛い。
無理して正座なんてしなければよかったかも……。
「崩してもいいのよ?」
「えっと……大丈夫です」
おばさんは正座しているのに、こちらだけ脚を崩すのは失礼な気がした。
「まどかちゃんは北海道は初めてなのかしら?」
「はい。こっちは雪がいっぱいでびっくりしました」
そうでしょうね。とにっこり笑うおばさん。
品のある微笑みは和服姿と相まって、やはり落ち着いた大人らしさが感じられた。
「すいません、わたしなんかがお邪魔してしまって……」
「いいえ。あなたが男の子だったら門前払いしてたかもしれないけど、可愛い女の子ならいくらでも歓迎だわ。じゅるり」
前言撤回。やっぱり残念な人だった。
でも、これがおばさんの本当の姿なのかな?
さっきは怖いって思ってたんだけど……。
わたしの気のせいだったのかな?
「まどかちゃんが来てくれてすごく安心したわ。あの子にも仲のいいお友達が出来たのね」
「わ、わたしなんかでいいのかなって思うところもあるんだけど……はい……」
「でも本当は恋人なんでしょう?」
「ち、違いますっ!?」
「ならどうしてそんなに赤くなってるのかしら?」
「えっ……」
「もしかして、まどかちゃんは片思い中だったりするの?」
「ちが……」
ほむらちゃんのことそんなふうに考えたこともないよ。
だって、わたしたちは女の子だし、そもそも恋ってのがまだよくわかってない。
顔が赤くなったのは、わたしがこういう話が苦手だから。
お友達のそういう話を聞くのはいいけど、話しを振られると困ってしまうからで。
「そう。残念ね」
あれ?意外と簡単に納得してくれた。
「じゃあキス。キスしたい? したいっしょ? 」
ダメだこりゃ……。
おばさんには黙ってるけど、わたしは毎日ほむらちゃんのお家に泊まってる。
ご飯を食べるのも一緒。学校に行くのも、朝ごはんを食べるのも。
それが知れたら、絶対誤解されるから。
たしかにお友逹……とはちょっと違うのかもしれない。
ただのお友逹が、毎日いっしょに暮らしたりしない。
同じベッドで、隣で寝たりしない。
そういう意味で、ほむらちゃんとわたしの関係は特別だった。
だけど、少なくともわたしは、ほむらちゃんのことをお友逹だと思ってる。
「ほむらちゃんとは、キスだってしたことないし、したいと思ったことだって…」
「なるほどねぇ」
ユキはまどかを見て意地悪く笑った。
「でも、ほむらはそう思ってないかもよ。なんてたって私の娘だもの」
「ほ、ほむらちゃんはそんなことしませんよ!」
「そうかしら? わからないわよ?」
妙に説得力のある言葉だった。
まさか、ほむらちゃんが?
『まどか……わたしあなたのことが』
「うわぁあああああ」
顔が熱くなる。寒気が吹き飛んでしまった。
「どう?」
「どう……って言われても……こんなのほむらちゃんじゃない」
「そう思っていられるのも、いまのうち」
ああ、完全に遊ばれてる。
ほむらちゃんとはそういう話をしたことがない。
お互いに恋愛経験がないから、話題にならないのかな。
わたしはそれだけじゃないんだけど……。
でも『キスしたい?』なんて聞かなくても、ほむらちゃんにそんな気はないことぐらいわかってる。
一緒に寝てるときにキスするチャンスなど山ほどあったはずだし、抱きついても声が揺らぐこともなかった。
それどころが、極めて冷静な口調で窘めてくる。
『あなたの鼻が胸に当たってくすぐったいのだけれど……』
『朝ごはん作るから、そろそろ離してくれないかしら?』
そんなほむらちゃんが、わたしを好きだなんてとても思えない。
だけど……子供みたいに甘えることをどう思ってるかは気になっていた。
「ほむらちゃんはそんなことしないです」
「そう……まあいいわ」
;【暗転】
;【居間】
「で、まどかちゃん。あなたにどうしても聞いておきたいことがあるの」
ユキは咳払いをして、本題に入ろうかという雰囲気を出した。
「その前に1つ。まどかちゃん。ここで二人でお話したことはほむらには内緒にして欲しいの」
どうしてですかと聞くと、神妙な顔でおばさんはこう答えた。
「まどかちゃんがこの正月に家にも帰らないでこんな場所に来ているのには、何か事情があるのでしょ?」
「それは……」
正月に帰るべき家がないから……。
「ごめんなさいね。聞かれると困ることがまどかちゃんにもあるように、私にもいろいろあるということで納得してもらえないかしら」
おばさんはここに来たこと何も言わず、認めてくれてたんだ。
確かに子供を持つ親が、年末に友達の家に泊まりにくることに不審を感じないなんておかしい。
それを暗黙で承知してくれてたんだ。
そう考えると、おばさんはよっぽど優しい人か……やっぱり変わった人なのかもしれない。
「すいません、私……」
「別に構わないわ。事情は人それぞれだものね」
ほむらちゃんのお母さんだけあって、本当は思慮のある人なんだと思った。
必要以上に踏み込んでこない。
今はそれがありがたかった。
「で、私の聞きたいこと……いいかしら?」
「なんでも聞いて下さい。わたしが知っていることだったら答えます」
「ほむらはどうして帰省する気になったのかしら? まどかちゃんに心当たりない?」
「えっ?」
質問の意味がよくわからない。
一人暮らしの娘が正月に帰省するというのは当たり前のことではないのか?
「ほむらちゃんが帰ってくることが不思議なんですか?」
そうね。とおばさんは笑った。
「およそ一年半ぐらい、一人暮らしをしているのだけど、今日まで一度も帰ってこなかった」
「えっ?」
ほむらちゃんの”過去”について、何もしらない。
昔のことを詮索しようにも、ほむらちゃん自身の記憶が曖昧なのでどうやって生きてきたのか、今まで何をしてきたのか。
「でも電話とかはしてたんですよね?」
「いいえ。一度も」
「一度も……って」
なんなの?
「おばさんは心配じゃなかったんですか?」
「それなりにはね。でも、そもそも帰って来なくていいって言ったのは、私の方だから」
わけがわからない。
「たぶん、まどかちゃんには理解が及ばないと思うけれど、私たちにも考えがあってやったことだから、そんな顔しないで」
「でも……あんまりだよ」
「そうね。自分でも酷い親だと思うわ」
後悔してるのかな?
そう思ったとき、おばさんの顔は一変した。
「ただ、半端な情けは、人のためにならないわ」
目はまるで修羅を潜り抜けた侍のように厳しい眼光を放っていた。
冷たい視線に晒され、背筋が凍った感覚に陥った。
衣の中に隠れた、もう一人の人間が顔をだしたかのように……。
「私たちはあの子に一人でも生きていけるぐらいの気概と精神を身につけて欲しいと思ったの」
驚きを隠せない。
目を開いたわたしを見ても、唇はぴくりとも動かなかった。
そんなおばさんに向かって、わたしは当てつけのように言った
「よかったですね。おかげで、ずっと強くなったと思いますよ。家を出たときよりずっと、ずっと」
「怒ってる?」
「少なくとも、わたしは”今”のほむらちゃんに助けられてるから。ずっとここにいたら、ほむらちゃんには出会えなかっただろうから」
そう。おかげでほむらちゃんに出会うことができた。
けど、おばさんの考えてること、ぜんぜんわからないよ。
この人は身体の弱い、しかも小学校から卒業したばかりのほむらちゃんを、家から追い出したんだ。
わたしだったらとても耐えられないのに。
事情があったかもしれないけど、連絡ぐらいはできたんじゃないの?
一言話せば、一言声を聞かせてあげれば……。
ほむらちゃんは、今こんなに苦しまなくて済んだかも知れないのに。
家族を忘れた悲しみを抱えることもなかったかも知れないのに。
「自分の為に泣いてくれるお友達が出来るなんて、あの子はきっと変わったのね……」
「わかりません。わたしはむかし、ほむらちゃんがどんなだったか知らないから」
「そう……」
その代わり、おばさんも知らないんだ。
“本当のほむらちゃん”のことを。
この人のことはまだよくわからないけれど、それが酷く悲しいことだと感じた。
「私が気にしているのはきちんと言い付けを守ってきたあの子が、どうして急にこの家に帰ってきたかということ」
おばさんは話しを続けた。
「本人が一人前になった感じているというのなら納得するわ」
「友達の少なかったあの子がまどかちゃんみたいな子を連れてくるなんて、思いもよらなかったし」
「細かく条件を出していなかったのだから、あの子が胸を張れるぐらいに成長できたというのなら少なくとも私は認めるつもりだった」
「けれど、何かしっくりこなくて……まるで約束自体を忘れてしまっているような」
思わずはっとなった。
なんて鋭いんだろう。と。
同時にしまったと思った。
「何か知っているのね。よければ教えてもらえないかしら?」
「私からは何も言えません……」
「娘のことを把握しておきたい母親の気持ちというのはまどかちゃんにもわかるでしょう?」
「なんでわたしに聞くんですか? そんなのフェアじゃないよ」
「……確かにね」
ふぅっと息を吐いた。
「けど、おかげでほむらが約束を忘れていることはわかったわ」
わたしは生涯、この人のことが苦手になる予感がした。
底の知れない怪物のようだった。
部屋に戻ると、ほむらちゃんはまだ布団の上で眠っていた。
こんなこと考えるなんて、本当は間違ってる。
それでもほむらちゃんが不憫に思えてならなかった。
「ごめんね、ほむらちゃん……いつも私のことを守ってくれてるのに、私……何の力にもなれなかったよ」
怖くて反論できなかった。
でも、絶対におかしい。
帰って来なくていいなんて、そんなこと言われたら、どうしていいかわからないよ。
そのときふとママのことを思い出した。
優しくてかっこよかったママ。
世界の理が歪められてもなお、わたしのことを憶えてくれていた。
思わず涙が出そうになった。
「世の中には、いろんなお母さんがいるんだね、ほむらちゃん」

ラテ・ラピクさん作
切ない気持ちに耐え切れず、布団に潜り込んだ。
そして、いつものようにほむらちゃんにすがるのだ。
そこにある温もりは優しく温かい。
なのに、胸に溶けていく切なさがわたしを飲み込んでいくのが止められない。
親の記憶はあるけれど、二度と家族には戻れない親子。
親の記憶がないのに、つながりがある家族。
どちらが不幸でどちらが辛いのかなんて、わかりそうもない。
だけど、ほむらちゃんがずっと笑っていられるように……。
わたしだけはずっと側にいよう。